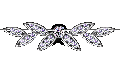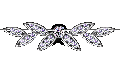Underground “Azi Dahaka”
<地下都市 “アジ・ダハーカ”>
40000HIT
Aya様に捧ぐ
世界には、秘密がある。
どうでもよかったり、どうでもよくなかったり、そんな秘密で溢れている。
当人は必死で隠していても、周りの人間にとったら何の足しにもならない秘密。知らなくともつつがなく人生を送れるであろう秘密。
そして──存在さえ知られていない秘密……。
休日の午前中。
レーテル都市の一郭である学生街の閑散とした通りを、彼女は颯爽と歩いていた。
「休みだってのにお昼の鐘が鳴る前に外を出歩く私。けなげ過ぎて涙が出る」
そう嘆息して目元の涙を拭(ぬぐ)う。……あくびだ。
黒のハイネックシャツに黒のスラックス。上から軽くワイン色のローブを羽織り、長い髪をかきあげるその女の名はレベッカ=ジェラルディ。言うまでもなく、この辺の人間ならば知っている名だ。知らなければモグリとも言える。
「派手な爆音でもさせて呑気に寝てる学生連中叩き起こしてやろうかしら。私だけ起きてるなんて癪(しゃく)だもの……」
レーテル魔導学校3年、ついでにメディシスタ生徒会風紀委員長。20を超えてなお我の強すぎるこの女、“風紀”という言葉からは誰よりも遠く離れているのだが、だからこそ風紀委員長の座に据えることで鎖に繋なげたかと、彼女の就任当時皆思っただろう。
しかし結局はただ、彼女に権力と大義名分を与えただけだったのだが。
と、レベッカは立ち止まった。
「あーあーあー、まったくいつ見ても嫌味にでっかい家」
彼女の見上げた先にはおよそ学生街にはふさわしくない大きな家──いや、大邸宅がそびえていた。
一体普通の学生アパート何個分の土地を費やしているのだろうか屋敷。それがただひとりのために建てられたものだというのだから心底からため息が出る。
白塗りの壁が妙にまぶしく、手入れの行きとどきすぎた庭が恨めしい。
そして肝心の所有者の名前は、メディシスタ生徒会会長シャロン=ストーンという。代々王都の剣士団団長を務める、剣ではこの世界並ぶ者なき名門ストーン家の長男だ。
財も力も有り余っている一族であり、あるいはもしかしたら──王都で一番力があるのは王でなく、この家なのかもしれない。
「メディシスタ、チェンバース、休日に集まって魔導大会の話し合いだなんてホントにもう……、時間外労働で訴えちゃうわよ」
長すぎる前庭を抜け、デカ過ぎる扉の前に立つ。
ノックではなく蹴っ飛ばしてやろうかとも思った彼女だが、欠片残っていた良識でやめる。
獅子の金輪を持ち八つ当たり気味に扉へと叩きつけた。
「はい、どちら様でしょう?」
「……え」
向こうで待機していたかのようにすぐさま開く扉。そしてその奥、思わず声を詰まらせたレベッカの前に現れたのは、メイド姿をした少女だった。真っ直ぐな黒髪に硝子玉のような瞳。人形と見間違うばかりだ。
「お約束はおありで?」
「……えぇと、私は風紀委員長様のレベッカ=ジェラルディ。お約束はおありよ」
てっきりこの屋敷にはシャロンしか住んでいないと思い込んでいた彼女だったが、常識で考えればストーン家の息子、そんなことはあり得ない。やらせればあてつけのように家事全般卒なくこなすだろうが、そもそもそういうお育ちではないのだ。
「ではこちらへどうぞ」
「…………」
くるりと踵(きびす)を返して奥へと向かうメイドをしばし見つめ、レベッカもそれに続いた。
外見の豪快さに比べて驚くほど簡素な邸宅の中身。敷き詰められた紅の絨毯こそ格の違いを感じるが、白い壁には絵画の一枚もなく。廊下には壺ひとつ、甲冑のひとつもなく。“飾る”だとか“見せ付ける”だとか、そういうことに無頓着な屋敷の主の性格があからさまに伝わってくる。
「こちらでお待ちください」
「──ここで?」
「えぇ」
案内されたのは、小さな部屋だった。
しかしレベッカが聞き返したのは他でもない、この部屋に違和感を感じたからだ。
(変ねぇ?)
彼女は胸中でつぶやき、静かに見回した。
悪い部屋ではない。趣味はいい。白いソファは座り心地がよさそうだし、木製の飾り戸棚も装飾が美しい。そしてその中に並べられた皿やグラスも相当に値打ちもののような気がする。奥に鎮座する柱時計も年季が入っていそうな重厚さ。
だが──、
(物が全部壁際にあるってどういうことかしら)
一歩二歩三歩。あごに手をやったレベッカはガランとした部屋の中央へと足を踏み入れる。
と。
「邪悪な気は成敗します!」
部屋の入り口で少女が叫んだ。
「──はい?」
レベッカは振り向きざま防御の呪を念じ──、しかし次の瞬間視界から景色全てが消え失せた。
……床が開き、落ちたのだ。
◆ ◇ ◆ ◇ ◆
「落下法則解除」
暗闇の中、咄嗟に口をついた呪が彼女の身体を浮かせた。
そのまま上昇することも可能だったが、床はもう戻されたのだろう、見上げる限り光は見えなかった。
彼女は腕組みをしつつ下降を続け、ブーツの裏が地面にあたると術を解除する。
「私が何したっていうの一体。お客にこんなことするなんてシャロンの教育がなってないせいよね。まさかただで済むと思ってないでしょうねぇ」
凄まじく常套(じょうとう)なやり方にひっかかってしまったことが腹立たしく、──が、彼女はすでにお礼参りの方法を考えていた。
「……犯罪にならないように嫌がらせするのって難しいわ……」
闇に目が慣れてきたところで彼女は歩き始めた。
ローブの裾が揺れるたび、細かい砂塵が足元を舞う。
地下遺跡のような──そうでなかったら地下牢獄だ──石積みの壁に、案外高い天井。どうやら先は突き当たりになっているらしく、曲がった右側から灯の光が見える。
そして──、彼女は大きくため息をついた。
「何なのよ、これは」
灯に誘われて歩を進めた先。レベッカ=ジェラルディの眼前に広がっていたのは、紛れもない都市だった。彼女の足元から奥へと大きく伸びた石畳の通りには、地上のレーテルと同じように数々の店が立ち並び人々が出入りを繰り返している。
酒場の看板、薬屋の看板、宿屋の看板、古書屋の看板……。積み上げられた酒樽や路肩に座り込んでいる酔っ払い、無造作に放り出された果実の芯が女の来る場所ではないと告げていた。
地上の都市で言えば裏路地のスラムのようなものか。しかしそれにしては、並んでいる店が立派過ぎる。
まるで表通りと裏通りが混在しているような──。
「お嬢さん、丸腰でこんなところをうろついていちゃあいけねぇなぁ。高くつくが……案内してやろうか」
ふいに、からかうような若い男の囁きが背後から耳をくすぐった。
「……三流役者。もっとマシな台詞思いつかないの?」
レベッカは腰に両手をあてて振り返る。
「アンタまでここにいるなんてね、──フェンネル」
「メイド人形に落とされた」
しらっとした顔で肩をすくめてみせるその男。軽装な剣士服の上から黒のインバネスを羽織り、剣士とも魔導師ともつかぬ曖昧な格好でこちらを見下ろし笑う。
その斜めな顔つきとエセ紳士な言動から黒のヴァンパイアと称される、チェンバース生徒会会長のフェンネル=バレリー。
「やっぱりあの子人形ね?」
レベッカが問えば、
「あの可愛い子ちゃんの動きにあわせて魔導の力が流れていたからな」
フェンネルがうなづく。
「気配のよろしくない魔の力に反応してここへ落とすプログラムが組まれてるみたいなんだな、どうも。俺はこいつのせいで落とされた、おそらく」
彼が腰に帯びた剣を見やった。
王都が血眼になって探し、返還を求めている魔剣【征服者<コンキスタドール>】。主を死に至らしめるという紅刃の剣である。実際フェンネルの父親はこの剣が元で亡くなっていて──。
「お前はなんで落とされたんだ?」
「…………」
レベッカは憮然(ぶぜん)と自分を見下ろした。
今日は呪符も持っていない。錫杖も持っていない。
「…………」
フェンネルが笑いを噛み殺して天を仰ぐのが視界の端に映る。
レベッカはそれを睨みやりながらつぶやいた。
「私自体が邪悪だっていうのね、上等じゃないあの小娘」
太陽ではなく炎に染められた地下都市。レベッカはこの街、レーテルに3年間住んでいながらこの存在を全く知らなかった。学校でも教えられなかったし、見知らぬ住所に出会ったこともなかった。少なくとも彼女が行きたいと思う店、友人の家が地上で見つからないことはなかった。
観光パンフレットにもこんな地下のことなど載っていない。
「……超法的都市だな、これは」
レベッカのいぶかしみを見透かしたように、フェンネルが口をはさんできた。
「非合法的都市ってわけじゃないのね?」
「シャロンの家からここに来られるということは、ストーン家はこの存在を知っているということだろ? 暗黙の了解ってやつだ」
彼が僅かに眉をひそめる。
「レーテルの下にこんなもんがあったとはな。……見ろよ、正真正銘の“竜の髭(ひげ)”が売ってやがる」
怪しげな店の窓をのぞきながら、彼が指差した。
光が落とされたランタンに照らされ、整然と並べられた棚の向こうのカウンター。その上に彼の言うそれは飾ってあった。人間何人分あるのだろう長さと、両手で掴んでなお余りあるような根元の太さをもつ、黒い髭。
この世界──シャントル・テアには存在せず、古の召喚法によってのみ呼び出されたという竜。その髭は変化や解毒、その他薬を扱う魔導師たちには珍重されてきた。今はもう王都の法によって竜の召喚が規制されているために、滅多なことでは店に並ばない。
「空魚(そらうお)までいるぜ」
棚の一郭に置かれた籠を見て、感嘆の声を上げるフェンネル。
「本物を見たのは始めてだ」
「……ブラックマーケットね……ここは」
空魚は遠い昔に滅んだとされる生き物なのだ。木々に囲まれた清い湧き水の付近にだけ生息していたと言われる、透き通った青の魚。光の加減によって鱗は虹色に輝くのだそうだ。
幻術に使われていたらしいのだが、詳細は学校所蔵の古き本にも記されていない。
あるのはただ、色褪せた絵だけ。
「こんな桁外れたレベルの魔導を王都が黙認してるってのか……? レーテルなんていう魔導師の卵しかいねぇようなところに目くじらたてておきながら」
「アンタが暗黙の了解だって言ったんじゃない」
「そりゃそうなんだけどよ」
ふたりが物珍しそうにあーでもないこーでもないと囁いていると、突然背後から野太い声がかけられた。
酒の匂いの混じった下卑た笑い声。
「兄ちゃんネェちゃん、一体何やらかしたんだ? こんなところに落とされるなん──っが!?」
その男が最後まで台詞を言うことはなかった。
肩に手をかけられたレベッカは、問答無用で裏拳を叩き込んだのだ。が、いかんせん相手は屈強。男は面食らったように二、三歩たたら踏んだだけで体勢を立て直し、顔を朱に染めてくる。
「こんのアマ──」
「止めときな」
「……っ」
フェンネルの蔑んだ声音と同時、彼の紅刃はすでに大男の首へと当てられていた。
彼がこのまま剣を引けば、いかに強力な男といえど失血死は免れない。ただの力は、生物学的な致命傷を超えられない。
そしてこのお兄さん、どちらかというとレベッカよりの危険な性格をしている。手加減ナシなのだ。
「聞きたいことがあるんだけどなァ、オジサン」
身長差ゆえにフェンネルが男を見上げてはいるが、立場の上下は反対。
「……見世物じゃないのよ」
レベッカが見回せば、人相の悪そうな輩たちが騒ぎを聞きつけて集まっていた。
どの顔も皆、指名手配のビラに描かれていそうなものばかり。
「目障りなの、分かる?」
しかしこんな小さないざこざに首を突っ込んでくる奴等なんて、裏路地のゴロツキ程度だ。
彼女がドスのきいた声で睨みやると、全体の輪が一歩退く。
そして、フェンネルが続けた。
「ここは一体何なんだ? テメェらは誰だ?」
「……アジ・ダハーカ」
「──はァ?」
「この地下都市の名前だ、アジ・ダハーカという」
ニヤけながら、大男が言う。
しかしレベッカはそれ以上に薄気味悪い笑顔を浮かべて、両手を腰にやった。
「古に召喚されて手のつけようがなかったっていうあの三頭の竜の名ね。……で、ここは何のためにあるのかしら。キリキリしゃべらないと命はないわよ。私は気が短い上に優しくないから」
「威勢がいいのはいいがな、ネェちゃん。そんなことじゃここでは長くもたねぇぜ」
「……無駄口はいらねェな」
強く押し当てられた紅刃に、大男が口をつぐむ。
「長くいるつもりなんざさらさらネェしよ」
「そうなのよ。早く行かないとシャロンにまたチクチク嫌味言われるわ。あの人、天然で痛いこと言うから嫌なのよね」
「本人嫌味言ってる自覚ないからな」
「相手の良心をグサッと突く、究極の方法よね」
「お前に良心があるとも思えねぇが」
「うっさいわね」
レベッカは吐き捨てて大男に向き直り、
「アンタがつまんないこと言うからいけないのよ。捕虜は聞かれたことだけしゃべりゃいい……って、よく映画でカッコイイ上官が言うでしょ? それで、ここはどういう場所なの? なんで地上じゃ違法なものが堂々と取り引きされてるの?」
「……ネェちゃんたち正規のルートで来たんじゃなさそうだな」
見るからに不法な男から“正規のルート”だのと言われる筋合いはない。
だからレベッカは無視した。
「聞かれたことに答えないとその魔剣がアンタの血を全部吸い取っちゃうわよ」
「このところ何も斬ってなくて飢えてるからな」
台詞を聞くに、どちらが悪者なのか分からない。
大体先に手を出したのはレベッカであるのに、完全棚上げ。
しかし脅されてビビッたわけでもないだろうが、別段隠すことでもないのだろう、男は素直にしゃべり始めた。
「……アジ・ダハーカ。ここにいるのは、地上で法を破って好き勝手やってたが、王都と手を組むことにした連中さ。王都はこの都市に住む俺たちに命の保障をする。俺たちはここで何をやっても絶対に極刑を受けることはねぇ。早い話が王都公認の無法地帯だ。そして代わりに俺たちは、王都が自身でやりたくとも体面的にできねぇことを裏でやってやる」
「例えば?」
「魔剣や魔道具、その他上では禁止されてる希少物の密売。その売上で王都の連中は潤う。それから王都にとって厄介な人物の暗殺、脅迫。裏金回し、組織潰し。それから、上ではできねぇような魔導の実験」
「……だから良心の欠片もなさそうな連中ばっかりなのね、ここ」
しらけた水平な視線でレベッカは周囲を牽制した。
壁のランタンの灯が揺れて、ローブの影もまたゆらめく。
「この地下都市アジ・ダハーカは、どれくらいの規模があるの」
「俺はこのレーテル地下から他へ行ったことはねぇが、主要都市の地下には必ず地下都市があって、それらは長い一本の地下通路でつながっている。王都はそれら全部をあわせて“アジ・ダハーカ”と呼ぶ」
「…………」
レベッカは眉を寄せた。
フェンネルもただでさえ悪い目つきを、さらに細めている。
つまりは──太陽の当たる地上をシャントル・テアと呼ぶならば、この地下世界すべてが“アジ・ダハーカ”である。そういうことだ。
それにしても、とんでもない事実があるものだ。
絶対的なひとつだと思っていたこの世界が、実は二面製だったとは。
「知ってたか?」
「いいえ」
「お前さんたちみたいなヒヨッコが知ってるわけねぇだろう。レーテルの御頭でさえ知らネェよ」
アジ・ダハーカ。
古の、扱いえぬ竜の名を冠した地下世界。
地上の人々は生を受けてからそれが尽きるまで、その存在すら知らずに終わる足元。
魔導師ならば心奪われる品が横行し、倫理という言葉などどこにもない異国。
力を求めてやまない狂った輩が禁書をめくり、魔剣を磨く。どこからかさらってきた生贄を祭壇にささげ、実験的な召喚を繰り返す。
「もしかして……今まで闇に魂を売った魔導師として名を轟かせ、捕まった連中。みんなここにいるわけ」
「街ひとつを滅ぼし捧げて禁書を召喚し、その力を得ようとしたかの有名なアルボル・ナルバートン導師は、ご老体だが今も王都の地下に住まわれている。誰が張ったのかは知らねぇが、ここの壁は強い結界で出来ているから、どんな魔術を使っても崩れることはねぇ。導師は王都の手厚い保護のもと、非合法な魔導実験をやりたい放題やり尽くされたって話さ」
「…………税金の無駄遣いだわ」
レベッカは額に手をあててうめいた。が、横からきっぱり否定される。
「お前まだ払ってないだろ」
「……父さんと母さんは払ってるもの。それに将来は絶対払わなきゃいけないのよ。こんなむさくるしいやつらを養うために!」
「確かにそりゃ気に喰わんが」
「大丈夫だ」
大男が、脂っぽい目でねちっと言った。
「ニィちゃんもネェちゃんも、税金なんて払わなくたっていいのさ」
『なんで?』
レベッカとフェンネルは唱和した。
ますます陰険な笑いで男が言葉を継ぐ。
「ここにいったん入っちまった奴はもう二度と地上へ戻れネェからさ。考えてみろ、秘密が漏れる」
『…………』
ふたりは顔を見合わせた。
「まずいな」
「うん、まずい」
『ここでいざこざして帰るのが遅れたら、シャロンに延々と説教される』
「だから帰れネェって──」
「おじさんどうやったら上に戻れる?」
「人の話を聞け!」
「聞いてるさ」
フェンネルが目を据えて僅かに剣を引いた。
男の首に血が滲む。
「だがな、そっちの都合は俺たちにゃ関係ねぇ。俺たちは帰らんわけにはいかないからだ」
「大体、レーテルからここへの入り口を守ってるのはシャロン=ストーンなわけでしょ? 敬愛する会長様を売るよーな真似するわけないじゃない。秘密厳守よ秘密厳守」
到底信じてもらえそうもない軽薄な口調で言いながら、レベッカは腰を低く落とす。
フェンネルも剣を男の首から離していた。
「どうやら……帰ろうとする人間は始末するって唯一の法律があるみたいねぇ?」
「理にかなった法律だけどな」
いつの間にか人だかりの種類が変わっていた。
ただの野次馬から、それぞれに危険物を手にした犯罪者へと。
「王都からの命令なんでね? 正規ルートを辿らないで入った奴は生かしておくな、ってね」
魔剣から解放された大男が、コキコキと首を鳴らして低く言う。
「悪く思わねぇでくれよ? 仕方ねぇのさ」
「悪く思わないわよ」
真面目な顔でレベッカも返した。
そして可愛子ぶった微笑みで肩をすくめる。
「だからそっちも悪く思わないでね」
「──おい、どっちの呪文にあわせる」
横から囁かれたフェンネルの声。
「もちろん私」
「了解」
大鎌だのヌンチャクだの棍棒だの、当たったら痛そうな輪がだんだんと縮み──
「やっちまえ!」
『悪人大粛清!!』
凶悪な笑みを浮かべたふたりが叫ぶや否や、倍になった爆炎が狙った場所へと渦巻いた。
かくて悪人ステーキ(真っ黒こげ)が大量に生産されたのである。
そのひとつをツンツンと蹴っ飛ばしながら、フェンネル=バレリーがつぶやいた。
「なぁ、この呪文考え直した方がいいぜ?」
「なんで」
「そのうち自分まで焼かれちまうぞ」
「……どういう意味よ」
◆ ◇ ◆ ◇ ◆
「遅い! 遅すぎますわ! レベッカ=ジェラルディだけならまだしもフェンネル会長までっ!」
「遅いですねぇ〜」
「寝坊したんでしょうか」
シャロン=ストーン宅の広い応接室には、三人の客人がいた。
ぷりぷりと怒っているのはチェンバース評議委員長のマグダレーナ=ミリオン。待ちくたびれてテーブルに伸びているのはメディシスタ副会長ネーベル=ケルトリア。慣れた様子で優雅に紅茶をすすっているのは、メディシスタ評議委員長ハイネス=フロックス。
「…………」
招いた当のシャロンも、時計を見やりながら足を組んで座っていた。
午前のおやつを食べながら会議をする予定だったのに、お昼になってしまう。困った……そう思いながら彼が立ち上がると、見透かしたように奥の部屋からけたたましいベルの連続音がした。
「……これは……何ですの?」
「来たんですかぁー? レベッカとフェンネル会長」
「──いや」
ぽつぽつと疑問符を上げる彼女らを制し、シャロンは応接室を出て廊下を走った。ポーカーフェイスはいつもと変わらないが、口元がかすかに緊張で結ばれている。
あれは鳴るはずのないベルなのだ。
誰も知らない、知らしてはならない、秘密を掘り起こすベルの音だ。
……王都最大の隠蔽(いんぺい)、地下都市アジ・ダハーカからの呼び出し音。
屋敷の一階に存在する不自然な部屋──全ての家具が壁際に押しやられた部屋──そこに入り、彼は後ろ手に鍵をかけた。
そして黒衣をひるがえし、クローゼットを開ける。
そこには、下からひもを引かれてうるさく鳴っているベルがあった。そしてフタがされた一本の金属管。
シャロンはとりあえずベルを押さえて音を消し、金属管を覆っていたフタを取った。
すると向こうから会話のようなものが聞こえてくる。
<こういうのがあるなら最初っから教えなさいよね>
<ったく、まわりっくどいことさせやがって>
「…………」
校内最強と歌われる黒衣の男は、眩暈をかんじて座り込みたくなった。だが、かろうじて踏みとどまる。
彼は己を押し殺し、下へ向かってマニュアルどおりに声をかけた。
「──こちらはレーテルのシャロン=ストーン。何か用か?」
沈黙。
そして一転、地獄の底から湧いてくるような呪詛が金属管を登ってきた。
サングラスで隠された紫眼が、凍りつく。
<シャ〜〜ロ〜〜ン〜〜〜>
THE
END
Menu Home
あとがき
この短編は、キリ番40000を踏んでくださったAya様に差し上げたいと思います。(おしつけ)
……あああ、どうも私はコメディな短編というのがとても苦手なようで……中途半端なテンションですいませんっ(汗)
地下都市というのが大好きな私でありまして、洞窟とか海底遺跡とか地底湖とか、そんな種類も大好きです。
「アジ・ダハーカ」とはゾロアスター教に出てくる竜なのでありますが、千もの魔法を扱うのだそうです。すご。
これ、実は結構重要な短編かもしれません。
そんなわけで、楽しんでいただければ幸いです。
Copyright(C)2003
Fuji-Kaori all rights reserved.
|