冷笑主義 番外短編
最後の騎士
前編
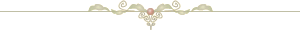
「言葉なんてものは、始めから我々を裏切っている」
彼がそう言った時も、
「そうかもな」
あの男は気のない様子で穴を掘り続けていた。
照りつける陽射しの中、クルースニクの証である純白の外套を乱すことなく身にまとい、穴を掘る。
その男の足元には、小さな箱が置いてあった。ただの箱と思うなかれ、細工も美しいインノケンティウス三世本人の私物だ。
「我々はこれを──剣と呼んでいる」
こちらを見ようともしない穴掘り男。しかしその横で佇たたずむ彼は全く意に介さず、自らの名が刻まれた聖剣を抜き、陽光にかざした。
「だが、こいつは剣と呼ばれようがペンと呼ばれようがお構いナシだ。我々がこいつをどう呼ぼうが、こいつは魔を滅ぼし、人を斬る。命を断つ」
穴掘り男が、小箱を穴に落とした。
今度はもくもくと埋め始める。
「鳥は、人と呼ばれたとしても空を飛ぶ。春は、冬と呼ばれたとしても花を咲かせる。言葉なんてのは“仮”に過ぎない。我々が知ったかぶって集めている言葉の寄せ集めは、人間が世界についた大嘘だ。世界は言葉など必要としていない。“約束”なんてものも、単なる言葉の羅列に過ぎない。意味はない」
彼がひととおり演説を終えると、男がようやく立ち上がった。
黒髪に長身痩躯の穴掘り男が眉を寄せる。
「ユニヴェール、つまりお前は何が言いたいんだ?」
つまりとかいう問題ではなく、この男はおよそ全部聞いていなかったはずだ。
それでも彼は穴掘り男に教えてやった。
「ロタール(インノケンティウス三世)が約束を反故にするのは今に始まったことではない」
「それくらい分かってるさ」
「それに裏切られたのは貴様ではないだろう」
「関係ない。ケジメなんだよ、ケジメ」
ふたりは気に入らないことがあると、腹いせに相手の私物をくすねてきては辺りかまわず埋めていた。
ヴァチカン、ローマ、フィレンツェ、オーストリア、フランス……派遣された先々、あらゆる場所に。
教皇下ヴァチカンの誇るクルースニク精鋭集団、その中でも一、二の実力を持つ彼らが腹を立てる相手は、高貴な者以外にない。
教皇を始め、皇帝、国王、諸侯、そして枢機卿。
そんな者たちからくすねた品々、いつか盛大に売り払ってやれば相当な額になることは間違いないだろう。
国家ひとつ買い取って大笑いしてやることもできるかもしれない。
「あの人は他人を裏切りすぎるからな。少し懲りた方がいい。罰だ、罰」
この日は、穴掘り男が上司である教皇インノケンティウス三世に腹を立てていた。
フランスに「イングランドを乗っ取れ」と囁いていたはずの教皇。しかし彼はその言葉を裏切り、すでにフランスが占領していたイングランドの領土を、かすめ取るように教皇保護領としてしまったのだ。
「……今時裏切りなんぞ珍しくもないだろうに。まったく、貴様の仁義には涙が出る」
「お前が一度でも泣いたことがあるか」
「そんなお人好しなことをやっているといつかその首取られるぞ、隊長殿」
彼は、剣の切っ先を穴掘り男の喉に向けた。
「我々は言葉というのものを“守る”ために発明した。それが例え“仮”であり、“嘘”であったとしても、世界というものを秩序だてて我が物とするには、それしか方法がなかった。だが今は──」
こちらを眺めている男の蒼い双眸に、自らの姿が映る。
男と同じ白い外套を羽織り、涼しい銀髪を風に揺らしているクルースニクの姿が。
「言葉など裏切るために存在している」
「…………」
「約束は、守られるか否かが問題なのではない。いつそれが破られるかが問題なのだ。裏切らねば裏切られる。家がひとつ滅び、国がひとつ消える」
「ユニヴェール」
男がため息をついた。
肩をすくめ、そして──……、そして……。
そして、あの穴掘り男は何と言ったのだったか。
世界にどんな嘘をついたのだったか──。
◆ ◇ ◆
時は中世十五世紀後半、まだ氷解けきらぬ春。
舞台は南フランスの片田舎、パーテル。
町の背後には、鬱蒼と広がる黒い森。入ればたちまち右も左も分からなくなるというその森の前には、立ち入る者を監視するが如く大きな古い屋敷が立っている。
昼間は人気もなく静まりかえり、メイドらしき少女が掃き掃除。
しかし一転暗い夜が世界を包めば、屋敷には煌々と明かりが灯り、森の奥どこからともなく不気味な馬車が訪ね来る。
あの屋敷には化け物が住んでいる──。
誰もが知っていた。
屋敷の主の名は、シャルロ・ド・ユニヴェール。
遠い昔からここに住み着いている彼は、生ける屍──吸血鬼だと言われていた。
そして、教皇庁がどれだけ手を尽くそうが滅びることのない、吸血鬼を遥か凌駕した化け物だとも。
クルースニクの銀剣で貫かれようが、首を薙がれようが、そして焼かれ灰にされようが、涼しい顔をして蘇る。
祈りの言葉も、神の言葉も、一笑に付す。十字さえ、嘲う。
冷ややかな銀髪、鋭く彫りの深い相貌。だがフランス貴族出身故の柔和な物腰。
華やかなる開花の時代。
歌は溢れ、物は流れ、金銀宝玉の採掘が進み、海は拓かれ、貴族は着飾り商人は大きな荷馬車を引く。言葉は惜しむことなく紡がれ続け、荘厳なるカテドラルを見上げる信徒の列は絶えない。
力強いまでに昏い暗黒時代。
権力を巡る戦いは数多の宮廷を巻き込み権謀術数渦巻き、髑髏が転がる焦土と荒野に虚ろな凱歌が響く。
神の代理人。その名のもとに魔の粛清は白さを増し、一方緋色の枢機卿は日々金を数える。
闇が濃ければ濃いほど、光はまばゆく輝く。
光が強ければ強いほど、──闇は深さを増す。
「ユニヴェール様、お呼びですか」
遠くで声がした。
「…………」
「ユニヴェール様、お呼びと聞きましたが」
声が近くなり、デスクでうつらうつらしていたシャルロ・ド・ユニヴェールは薄っすらと目を開けた。鮮やかな紅の双眸を二、三度瞬かせ、半分呆けた眼差しを声のする方へと向ける。
「あぁ?」
そこには彼のメイドが立っていた。
黒く長い髪に、平坦な黒い瞳。すっかり板についた灰色のメイド服を身に付け、こちらを見下ろしている。
「あぁ? じゃありませんよ。変な時間に呼び出されるから何事かと思えば──」
“変な時間”。確かに変な時間だろう。
レースのカーテンが揺れる窓の外を一瞥して、ユニヴェールは喉の奥で笑った。
陽は高い。本来ならば吸血鬼は柩の中で大人しく眠っていなければならない。
脆弱な吸血鬼という種族は陽光に焼かれて灰になってしまうからだ。脆弱でない彼にとっては、全くもって他人事だが。
「まだお休みになっていなかったんですか」
言いながら灰色メイドはツカツカとやってきて、盆に乗せていたとグラスをダンッと彼の前に置く。橙色の液体が波々とつがれたグラス。よっぽど冷やされていたのか、グラスはいくつもの水滴をつけていた。
「……パルティータ」
それがメイドの名前だった。
パルティータ・インフィーネ。
「親の仇のようにこれでもかとすりおろされたにんじんを、女の甘い血の代わりに飲めというのは無理がある」
「蜂蜜入りです」
「……糖分のことを言ったわけではないんだが」
細く長い指でデスクをコツコツと叩いてやると、
「それで、何の御用ですか?」
パルティータはいつものように無視してきた。
とてもメイドの態度とは思えない。が、気にしていても仕方ない。
あきらめて、彼は一通の封書を滑らせた。それはデスクの端でぴたりと止まり、彼女がつまみ上げる。
「……お誕生日会のお誘いですか?」
中身に目を通した彼女が、怪訝そうな顔でやや首を傾げてきた。
「ブルゴーニュ公からだ」
「……ブルゴーニュ公? あぁ、ローマ皇帝のご子息の……」
「マクシミリアン」
言って、ユニヴェールは再び窓の外を見やる。
雪のないところでは、小さな花々が蕾をほころばせていそうな陽気だ。何百回目かの凍てついた季節も、もうすぐ終わるのだろう。
「あの男も若いのに苦労者だよ。ブルゴーニュに婿入りしたはいいが、たった四年半で溺愛していた妻に死なれ、その深い傷も癒えぬうちに、所詮は婿、所詮はオーストリアからの余所者、フランスにそそのかされたブルゴーニュ・フランドルの都市たちは次々反マクシミリアンの旗を掲げて蜂起したときたもんだ。あげく最愛の息子フィリップは蜂起の中心都市“ガン”の保護下に置かれているし、最愛の娘マルガレーテは人質同然にフランスの掌中にある」
吸血鬼は戯曲の台本を朗読するように並べたてた。
「マルガレーテ嬢はフランスのシャルル王とご結婚なさっているのでしたっけ」
「とりあえずはな」
意味深な冷笑を浮かべ、ユニヴェールは背もたれに深く身を預けた。
「その結婚がマクシミリアンと今は亡きフランスのルイ11世との和平の条件だったはずだが──裏切りは常套手段、奥底に打倒ハプスブルクを掲げるフランスの毒蜘蛛ルイは、休戦協定を破って進軍したんだよ。その結果がこれだ。あちこちから攻められ抵抗されてローマ帝国皇帝の皇子ともあろう者が風前のともし火、敗北宣言寸前になるなど、誰が予想しただろうかね」
「それで──」
「パルティータ、お前、私の遣いでフランドルのオウデナールデへ行って来い。お誕生日会はそこで開かれる」
機先を制すと、平素表情を見せることの少ない彼女の顔が、しかめっ面になっていた。
「オウデ……どこですかそれ」
「ブリュッセルの近くだ」
「遠……」
「私の馬で行けばすぐだよ」
眉が寄せられていたパルティータの顔が元に戻る。そして開かれた口から出てきた言葉は、ユニヴェールの予想通りのものだった。
「出張手当は──」
「つく」
苦味を混じえてそう言った後、一拍置いて彼は含んだ微笑をメイドに向ける。手紙の続きなのか、一枚の紙切れをもてあそびながら。
「皇子は今、突き落とされた崖下から這い上がりつつある」
古びた紅玉色をした、穏やかな目。生きて数十年、死して数百年、年季の入った視線。
「お前は、あの男をどう評価するだろうな」
◆ ◇ ◆
『父公に死なれたブルゴーニュ公女マリアは窮地に立たされていた。反抗する都市民、裏ではフランス・ルイが巧みな糸を引き、領土を奪おうと侵略を始める。
そんな彼女の苦境を救ったのが、神聖ローマ帝国皇帝フリードリッヒ三世の子息であり、彼女の婚約者であるマクシミリアンだった。
千数百名にも及ぶ彼の一行がライン川を下り、ブルゴーニュ領にひとたび入ると、人々は熱狂的に彼を迎え入れたという。主の急逝に混迷を極めたブルゴーニュに現れた救世主だと、彼の行く道は賛辞と喝采で前も見えず、街には無数の旗が掲げられ、夜の闇は燃え盛る松明たいまつの炎で照らされた。
銀の甲冑に身を固め、颯爽と前を見据えて白馬の歩を進める若き皇子の姿は、まるでかの白鳥の騎士、ローエングリンかと思われるほどだった。』
「ローエングリンとはまた大きく出たわね」
つぶやき、パルティータはバサリと本を閉じた。本と言っても、ただ紙束を紐ひもでくくっただけの史記である。主の友人である文筆家が書いたものらしいが、記述がいささか誇大で古臭かった。
しかもそれほど昔のことでもないのに、この内容はすでに懐かしい幻想と化している。
公女マリアはすでに事故で逝去しているし、マクシミリアンがこんなにも歓迎されたのはもはや過去の話。たったの数年で、民衆は皇子を追い出しにかかっている。
しかしマクシミリアンという男は、打ちのめされて背を向けすごすごと家に帰るような若者ではなかった。
口端を噛みしめじっと時を待ち、そして反撃を始めたのだ。
反逆都市ユトレヒトを落とし、クレーフェ、アルンヘム、ゲルデルンを落とし、つい先日、件のオウデナールデを落としたところらしい。
破竹の勢いとはこのような状態を言うのだろう。
「そんな危険な所へいたいけなメイドをひとりで遣いに出すなんて紳士の風上にも置けない」
ユニヴェール所有の黒い馬車に揺られながら、彼女はぼそりと毒づいた。
正確には、主は別ルート──帝国領アーヘンへ寄ってくると言っていた──で来るらしいのだが、何をしに行ったのやら。
「パルティータ様、着きました」
揺れが止まったと思ったら、低い声がして馬車の扉が開けられる。顔の半分を磁器の仮面で隠した黒マントの男が手を差し出していた。骨だけの、手を。
「ありがとう」
これくらいのことをイチイチ気にしていたら、吸血鬼のメイドなどやっていられない。彼の部下には奇妙な化け物が多いのだ。
彼女はお姫様よろしく馬車から降り、目の前にそびえる石の要塞を見上げた。
遥か上ではためいているのは、ハプスブルク家の紋章“双頭の鷲”が描かれた軍旗。
背景は夜だった。月も、星もない完璧な夜。
誰が建てたのかも定かではない堅牢な戦城は、無愛想に無言。
お誕生日会をやっているのではなかったかと首を傾げれば、風の向きが変わり一瞬だけ騒がしい歓声が耳元を過ぎてゆく。
「しばらくすればユニヴェール卿もお着きになるかと思いますが、お待ちになりますか?」
「そうね……」
御者に問われて視線を足元へと落とすと、
「貴女がユニヴェール卿のお連れ様、パルティータ・インフィーネ嬢でございますか?」
突然甲高い男の声が響いた。脳裏をよぎった印象は、夜中の向日葵。
「…………」
顔を上げれば、案外的外れではない極彩色の化け物が立っていた。
先っぽに鈴のついたトンガリ帽子。ひょろりとした体躯を彩るのは目の痛くなるような色使いのダイヤ柄衣装、足元もトンガリ靴。
──道化師だ。
「それだけの物をお召しになれるのは、世の中広しと言えどもかの御仁のお身内だけかと存じます」
「…………」
その言葉は言いすぎだったが、確かに、パルティータの主が彼女のためにあつらえてきたものはなかなかに高価だった。たかが公国の君主──しかも落ちぶれた──と会うにしては。おまけに“誕生日の祝賀”という本来の主旨を全く無視した、いかにも吸血鬼一味な趣味でもあった。
膝丈までの黒ドレスは総ビロード。意匠には惜しげもなく黒レースが使われまくり、縁取る刺繍の金糸銀糸はすべて本物。
そして首飾りはダイヤとルビーが連なる骨董品。
長い黒髪を飾るのはこれまたダイヤがあしらわれた黒レースのヘッドドレス。決して枯れない深紅の薔薇が付いている。
主は自分が用意したにもかかわらず、仮装大会かと大笑いしていた。
失礼な。
「私はクンツ・フォン・デア・ローゼンと申します。ブルゴーニュ公の道化でありますから、一時だけでも信用してくださいませんか」
たしかに高貴な人々は専属の道化師を持っていることがある。
どうしたものかとパルティータが傍らの御者を見上げると、
「…………」
彼もまたどう反応したらいいのか分からないのだろう、肩をすくめてくる。
主には、いい加減な手下も多い。
「我が君が貴女とお話ししたいことがあると申しております」
「ユニヴェールではなく?」
「貴女です。卿へのお手紙にも付け足しておいたのですが。公は貴女ともお話がしたい、と」
それで主は寄り道して遅刻なわけだ。
「…………」
ローゼンのおどけた白塗りの顔。真意を読んでやろうと沈黙してじっとうかがえど、彼の黒い目の奥までが悪戯っぽく笑んでいて何も見せない。
「議題は何ですか」
「ユニヴェール卿を討つべきか否かについて」
彼はサラリと言ってきた。
「へぇ」
しかし言われたパルティータも顔色ひとつ変えなかった。
「さァ、こちらへどうぞ」
道化が大仰な仕草で城門の奥へと彼女を促す。
「分かりました」
彼女は案内されるまま、紋章はためく城へと乗り込んだ。
Menu Next
執筆時BGM by J.S.Bach [プレリュード 平均律クラヴィーア曲集第2巻 No.24 H-moll]
Copyright(C)2004 Fuji-Kaori
all rights reserved.
|