第24話 The Blessed Blood
後編
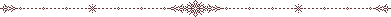
「貴方は今お噂になっている聖騎士様でしょう? みんなそう言っています」
一日の調査を終えて教会を出たところで再び花売りの女に会ったソテールは、定型な挨拶を交わした後で突然そう言われた。
「お噂?」
「お嫁さんを探しているって」
──マスカーニ!
「確かにそういう話はあるようですが、聖騎士なんてヴァチカンにはたくさんいて誰のことやら……」
「きっとどこかのお姫様が嫁いで来られるんでしょうね。みんなが色とりどりの花びらを建物の上から馬車に降りかけて、聖歌隊が歌って、美味しいものが振る舞われて、うるさいくらいの音楽に合わせて着飾った人たちが踊るんだわ」
春の清々しい陽光も、地平に降りる時間にはその清廉を焼くような黄昏色に変わる。
しかし晴れの日が続き、地平を染める光に足を止める市民の姿は少なくなってきた。
「それは幻想ですよ」
あの庭はある意味魔窟だ。
妃には、自身の家と国からの期待が圧しかかるだろう。その妃を介して自らの地位を上げようとする貴族や国や枢機卿が笑顔ですり寄ってくるだろう。わずかの不祥事を狙って妃とその家、その国を貶めようと謀略を巡らす一派もあるだろう。教会は民衆の支持を得るため、教会の望む妃であることを第一に求めるだろう。
彼女が期待される妃像は矛盾をはらみ多様で、何を決定してもどこかから恨まれる。
何も決断できなければあからさまに失望される。
それに耐えられれば良し、耐えられなければ己の義務を疎むようになり、やがてあらゆる厄介事を自分の視界から締め出し、誰かにすべての決定を一任するようになる。
古からその末路に明るい話はない。
「あの子は不器用なんです」
突然話が飛び、女の視線が自分の子どもに向けられた。
赤い光に染まる教会の壁際で、男児はソテールが土産に与えた人形でひとり黙々と遊んでいる。
「夫は“コイツはダメだ”しか言わなくて。夫が仕事にいかないのなら、これからあの子が一家を支えなきゃやっていかれないのに」
あの子は家族以外の人とうまくしゃべれないんです、そう言って女はため息をつく。
「貴方のお嫁さんになる人が羨ましい。少なくとも私みたいな心配はしなくていいんですもの。旦那様は人々のために尽くす誇り高いお仕事をお持ちだから」
「そいつは先日一回クビになりましたがね」
ソテールが吐いた自嘲気味の一言に彼女は反応しなかった。その代わり、
「どうして私は貴族の娘に生まれなかったのかしら」
諦めの笑顔で教会を振り返る。
「…………」
あの男ならクルースニクだった時代から言い放つだろう。
──そんなことは疑問に思うだけ無駄だ、と。
その出自に最も翻弄された人間のくせに。
呵々と笑う残像を振り払い、彼は女の後姿に向かって言った。
「貴女なら、職人の妻の苦労を乗り越えられると神に期待されているんですよ」
世界は決して平等ではない。どこかで辻褄が合うはずだという人間もいるが、その思想に科学的な根拠が与えられたことはない。
彼方神話の時代、テヴェレの川に流された幼子がパラティーノの丘に都市を築いた。それは人を呼び、文化を育み、戦いを繰り返し、強大になったかと思えば衰退し、長い年月の後に帝国はやがてこの地から離れてゆき、今では皇帝ではなく教皇を頂く。
幾多の血が流された時も、大工たちが朝から晩まで家を造り急速に町が広がっていった時も、不穏と疑心が蔓延した時も、華やかな祭りに市民が熱狂した時も、この夕陽は平等に都を照らしていた。
人生の幸不幸が不平等だとしても、大河の変遷の中にあって変わることのないこの美しさに寄り添えない者は、きっと不幸だ。
◆ ◇ ◆
「まさかアルプスを越えてローマにやってくるとはね。女を集めているのはイタリアの貴族か?」
世界がまどろんでいる昼下がり。
パーテルよりも暖かいローマではいたるところでミモザの黄色い花が満開になっている。そよぐ風も軽やかで気持ちがいいが、多くの人間が休憩を取っているのか街にいつもの活況はない。
「闇の王の情報網も頼りないものだな!」
不滅の吸血鬼とパーテルの聖騎士は蜘蛛の糸のように細い細い情報をたぐってここまでやって来た。
「仕方あるまい、向こうにも人為らざる者がいたんだろうよ」
パルティータが乗ったという馬車は商人たちが使う王道コースをほとんど通らなかったため進む街道から行き先を推測することが困難で、拠点への先回りも空振りに終わった。
それどころかユニヴェールが手先の魔物たちに探索を命じても、わずかの目撃証言を得るのが精一杯だったのだ。
「賊に魔物が混じっていれば、そこかしこにある暗黒都市との境界面を使うこともできるからな」
ユニヴェールが額にかかった銀髪をはね上げ、眩しそうに太陽を仰ぐ。
あれから数日経っているが、男に焦燥の色はない。
「パルティータの血が流れればすぐ分かるさ、逆に流れていないからこそ居所が掴めんのだが……」
「流れたらマズイだろう」
「あぁ、マズイ」
というわけだ。
「しかしユニヴェール、お前もまずくないか?」
「何が」
「ここはローマだ。聖騎士もクルースニクもうじゃうじゃいるぞ、もめたら面倒だ」
もはやヴィスタロッサの中には“ユニヴェールが滅ぼされる”という概念はない。
「そうだな。おまけにいつも上手いことやってくれるはずのアスカロンは旅行中ときている。実に面倒だ」
長身黒衣の麗人と金髪聖衣の女がローマの街角で立ち話をしていることがすでに目立っているのだが、どちらも自分のことは棚に上げるタイプなのでそのことは気に掛けていない。
「どうせだったらソテールを呼び出して探させるか。あいつ今ヒマだから」
「ヴェルトール隊長はヒマではない!」
「オートクレールだか何だか知らないが、余計な部署を作って金を使って、寄進を脅迫するのだけは得意なんだよ、ヴァチカンは」
教皇庁に税金を払っているわけでも寄進しているわけでもないユニヴェールが舌打ちし、それと同時、突然、数本先の路地から大勢が喚く声がした。
午後の微睡を裂いて男の太い怒号が響き、馬が次々いななき、複数の女の甲高い叫び声が上がる。
「!」
ヴィスタロッサは息を止めて目を見張った。
通行人たちも驚いた表情で辺りを見回し、自分の視界にその元凶はないかと探す。
もちろん、その火の粉が自分に降りかからないよう素早く退散するためだ。
「何を今更驚いているの!? 貴方たちは選ばれたんじゃなくて売られたのよ!」
ローマの乾いた建物をいくつか隔てても朗々と天に刺さるこの声は、
「パルティータ!」
ヴィスタロッサは言うや駆け出し、首根っこを掴まれ急停止した。
「ユニヴェール、何を」
「相手は賊で魔物が混じっているかもしれないというのが我々の見解だったはずだ」
「それがどうした」
「……こういう時は私が先、お前が後に決まってるだろう」
ユニヴェールが頭の悪い人間と話すと疲れるという顔で見下ろしてくる。
「バカにするな!」
思わず頭にきて振り払って剣の柄に手をかければ、
「理論的に考えろ。私は刺されようが薙がれようが死なない。だがお前は死ぬ。だったら私が先に行く方のが戦術として当然だろう」
さらに呆れた色でため息をつかれた。
「──いいか、その足りない頭蓋の中身のために何度でも言ってやる。お前たちは簡単に死ぬ生き物だ。選ばれた地位があるからって驕るなよ、首の骨が折れれば一般人もお前たちも同じなんだ、ころっと死ぬ。聖なる狩人は死を畏れず立ち向かうのが正義だとするかもしれないが、お前たちの仕事は死ぬことではないはずだ。正義に義理立てした行動を取っても意味はない。自分の望む結果を得るために何をすべきか考えろ。そしてそれを実行しろ。頭を使え!」
そもそも吸血鬼には生命維持としての呼吸が必要ないわけで、息継ぎなどなく小言が並べ立てられる。
「吸血鬼のくせにクルースニクの心得を説教するな!」
そして、ヴィスタロッサが地面を踏み鳴らした時にはもはや黒い影はいない。
「私を置いて行くな!」
抜剣して空をひと振り、彼女は真昼の吸血鬼を追いかけ──
「……なんだ? これは」
細い生活路地を抜けた先のやや大きめの通りでその騒ぎの一団を見つけた。
扉が開け放たれた大きな四頭引きの馬車。落ち着きのなく首を上下させている覆面の青毛が四頭。御者の姿はない。
馬車の周りでは若い女たちが半狂乱になって泣きわめき、土埃舞う地面に座り込み、中にはヒステリックに怒鳴り散らしている娘もいた。見た目はどこかの令嬢のように飾り立てられているが、言葉には色々な地方の訛りがあって洗練されてはいない。察するにパーテルやその近郊から集められた孤児院の娘たちだろう。
「パルティータはもういない。元々は我々が思うより機敏らしい」
颯爽と先陣を切ったユニヴェールは、地面に伸びている数人の男の上に腰かけていた。
下敷きになっているのは明らかに武装している賊だが、生死は定かではない。
「賊はこれで全部か?」
「こんなことは飽きる程繰り返されている」
建物によって陽が遮られ、吸血鬼がつぶやく場所は陰っていた。
「ユニヴェール」
「貧しさや苦難から抜け出す方法はそう多くない。ほとんどの者が、絶壁を登ろうとするより、垂らされた綱に掴まるだろう。その綱を引き上げようとしている者の姿が分からなくとも」
「…………」
低い独り言のようなそれは放り出されて悲嘆に暮れている女たちに向けられていたのだと、ヴィスタロッサは口をつぐんだ。
「貴族が孤児院から子どもを拾う時、それは婦人の不注意で子どもを死なせた時だ。夫に知られる前にすり替えねばならない。だが孤児院から花嫁を選ぶことはしない。孤児院の特定の人間をよほど気に入ったのだとしても、結婚するためは家を捨てる覚悟が必要になる」
「……愛人のようなものだと言われたの」
座り込んでいた娘のひとりが返す。
「愛人の必須条件は若さだ。歳を重ねたらどうなるか想像できないのか?」
「捨てられないように愛されればいいって院長先生は言っていたわ。跡取りを産めばもっといいって」
別の娘が涙声で反論し、
「あぁ、そうだな、そのとおりだ」
ユニヴェールが感情なく応えていた。
「おそろしく運がよく正妻に子どもがなくてお前たちが男の子どもを産んだとする。貴族の世界では何が起こるか分かるか? ──お前たちも子どもも正妻の家に殺される。それがごく一般的な正しい流れだ。当然のことだから、お前の死骸がテヴェレ川に浮いていたとしても誰も咎めないし、裁かない」
ヴィスタロッサもそのくらいは知っている。
それを歯に衣着せず淡々と言い放つのがこの吸血鬼の性質で、今更治療しようとするのは労力の無駄だ。過去、そんなユニヴェールの人間から逸脱した部分を補っていたのがソテール・ヴェルトールなのだろうが、その役割を果たす気は彼女にはなかった。
「浅はかな人間が多いおかげで魔物はエサに困らん」
「彼女たちを集めたのは魔物か?」
「さぁな。この手の事件は山ほどあった。黒幕が魔物のこともあれば、人間のこともあったさ。魔物には狩りをしないでエサを集める利口な奴もいる。人間には人間を生きたまま刻むのが趣味の奴もいる」
「…………」
ヴィスタロッサが眉をひそめると、
「人間にとっての最大の加害者は人間と神だ」
ユニヴェールが鼻先で笑って立ち上がった。
「魔物にとっては?」
ヴィスタロッサの問いは吸血鬼にとっては想定外だったらしく、幾分かの興がのった麗貌を向けられる。
男はしばし観察するような眼差しを見せ、そしてそのままの表情で言った。
「魔物にとっての最大の加害者は魔物だ、考えるまでもなく」
「クルースニク」
「そうなるように努力をしろ。お前がな」
「どうしてそれを!」
思わず脊椎反射で言ってしまってから慌てて口を閉じると、死人の口端が皮肉げに吊り上がった。
「ソテール・ヴェルトールはデュランダルを追い出され、しかしヴァレンティノ・クレメンティを呼び戻してオートクレールを作った。だが、デュランダルの人間を引き抜くことまではできなかった。あのお人好しが何をやりたいのかは知らないが、二名では動くに動けまい。奴には手駒が必要だ。一方で私のところには新しくパーテルに赴任するという聖騎士夫妻から挑戦的な挨拶状が届いていた。そこには夫妻両名とも聖騎士だということと、シルヴァン・レネックとヴィスタロッサの代わりだということが書かれていた。そしてお前自身だ。お前はパルティータを探してここまで来た。本来なら捜索は私に任せて途中の町でパーテルへ引き返してもいいはずなのに、何故ここまで付いてきた? それはお前自身が近日中にパーテルを離れるからだ。人間は感傷的な生き物だから、自らそれを伝えたいと思ったのか離れる前に会っておきたいと思ったのかは知らんが」
ユニヴェールの銀髪をローマの埃っぽい風が乱す。
その下で紅の双眸がゆっくりと瞬く。
「このふたつの現象は結びつけることができる。ソテール・ヴェルトールはオートクレールの強化のためにお前をクルースニクとしてヴァチカンに召喚した。仮説はいくらでも羅列できるが、最もらしいのはこれだ。違うか?」
「……そのとおりだ」
口外を禁止されているわけではないが、吸血鬼に報告するような話ではないと思って黙っていたのだ。
「クルースニクとしての訓練を受けて合格する必要はあるが」
「パーテルに送られてくる聖騎士でクルースニクの資質がない奴はいない。食屍鬼やヘルハウンドを追い払える程度の聖騎士がいたって意味がないからな、あの町は。何せ、暗黒都市が真正面から進軍してきた時には、まずはパーテルにいる聖騎士隊だけで闘って時間稼ぎをする必要がある」
ヴァチカンが報を受け取り、対応を決め、白十字やデュランダルが馬を駆り救援にやってくるまでの長い間。
それは勝利のための闘いではなく、自らの屍をもって軍靴の進みを遅らせるための闘いだ。
パーテルもまた、生贄の町。
闇と光の境界に存在する世界の防波堤。
「だがクルースニクでいるには別の覚悟が必要だ。いつ如何なる場合でも、クルースニクは魔物より人間を優先しなければいけない。その魔物がどんなに心優しい輩でも、止むに止まれぬ事情があったとしても、魔物の言葉の方が正論だったとしても。優先すべき人間がどんなに憎い奴でも、救いようのない奴でも、民を虐げていた王でも、王を裏切っていた臣下でも、人間を切り刻むのが趣味の輩でも」
ヴィスタロッサは抜け殻のようになって地面に座り込んでいる娘たちを見下ろした。
彼女たちを集めていたのは魔物か、それとも人間か──。
「クルースニクが信じるべきは神ではない。人間を信じ、そのための墓標となる覚悟がいる」
一連の出来事に飽きたローマ市民は、すでに日常の生活に戻っていた。職人たちは槌を打ち、商人たちは驢馬を引き、振り売りたちは声を張り上げ、路地の暗がりでは乞食がゴミを漁る。
吸血鬼の低い言葉は溢れる生活音に紛れていく。
「そうでなければ世界はすべてを失うだろう」
吐息混じりの囁きはきっと他の誰にも聞こえていないのだろう。
「私はその狭間で苦しむお前たちを眺めるのが好きだからね。それが生きている者の宿命だ」
「……悪趣味!」
ヴィスタロッサが顔をしかめて言い放つと、対して男は一度大きく手を叩いてにこやかに笑ってきた。
「さぁヴィスタロッサ、この女どもをローマの衛兵に引き渡して来い。ここに置き去りにするとローマ経済の邪魔になる。どう扱われるかは知らんが、次期オートクレールのメンバーが直々に依頼したのであれば、ひどい処遇にはならんだろうよ」
……切り替えが早すぎる。
彼女は自慢の金髪をわしゃわしゃとかき上げ、頭をぶんぶん左右に振り、大きく息をついてから再度ユニヴェールを見た。
「分かった。しかしパルティータはどうする」
「あいつがここで騒ぎを起こしたということは、ローマが目的地だったということだ。そしてあいつは、甘い言葉に踊らされた女たちに激昂していた」
吸血鬼が両手をあわせながら歩いて来る。
そして彼はヴィスタロッサの背後にまわり、両肩に手を置いてきた。
「そのふたつの点で思い出した女がひとりいる。大昔、私がまだ生きていた頃の話だが、おそらくそいつがパルティータの中に入っているんだ。だとしたら、目指しているのは──ソテール・ヴェルトールだ」
◆ ◇ ◆
ここ数日、花売りの女の姿が見えなかった。
もしかしたらこの辺りを縄張りにしている同業者に咎められたのかもしれない。彼らの相互自助の力は強く、同時に排他の力も強いのだ。見逃してもらっている間はいいが、目をつけられた時点で素直に彼らの領分を出て行かないと、それこそこの界隈では生きていかれない大変な事態になる。
──場所を移しただけならいいが。
思いつつ遅い昼食を取ろうと教会の外へ出て、ソテール・ヴェルトールは足を止めた。
外は文句の言い様もないくらい晴れ渡っていた。世界に溢れているその明るい光のせいで、おそらく実際の気温より皆暖かく感じているのだろう、冬装から一枚脱皮した装いの人間が多い。
丘は一面伸び始めた緑に覆われ、蒲公英がそこかしこで群生し、スミレが可憐な花を咲かせ、蜜蜂が飛び回って早くも真面目に仕事を始めている。
しかしソテールが足を止めたのはようやく訪れた心浮く春を愛でるためではなかった。
その長閑な風景の中にはいるはずのない女が立っていたのだ。明らかに彼を待っていた様子で。
「パルティータ・デ・コンティ──」
「ヴェルトール様!」
「!?」
立っていたのはユニヴェール家のメイドで、しかも彼女は地上を覆う春に劣らぬ朗らかな笑みをたたえ、あげくの果てにこちらを見るやすごい勢いで駆け寄り抱きついてきた。
「ヴェルトール様! もう一回だけでいいからお会いしたかった!」
「は?」
「どれほどこの時を夢見ていたか!」
彼女はこちらの両手を取り、握りしめてきた。
元々体温が低いのか長時間外気にさらされていたのかその手は冷たく、熱は彼女の方へと流れていく。
「……ずっと、ずっと待ち続けていました」
感極まりすぎて声は震え、彼女はそれだけを絞り出すとこちらをじっと見つめてくる。
ソテールは過度の期待と感激が入り混じるその視線に耐えられず、
「……人違いでは?」
穏やかに笑って引き剥がそうとしたが、
「わたくしがヴェルトール様を間違うはずがありませんわ」
きっぱり断言される。
だがそもそもユニヴェール家のメイドとは数回しか会ったことがないし、これほど好かれる理由も思い当たらない。第一、ジェノサイドのど真ん中で目を据えていた印象が強すぎて、どうしても眼前のきらきらした娘と結びつかない。
「でも、貴方がわたくしをお忘れでも仕方のないことです」
──忘れるわけがない。
数日前に自分の結婚相手として冗談でも名の上がった女を。
「落ち着け」
それは女に対して言ったのか、自分に対して言ったのか。
ソテールはもう一度引き剥がそうと彼女の肩にかけた手に力を込め、
「お前、落ち着けぇぇぇ──ッ!」
絶叫した。
彼女の主である吸血鬼が黒衣を翻して空から降ってきたからだ。
衆人の目が蒼い空に滲んだ黒い影に集まり、それぞれが口をぽかんと開ける中、男は軽い音で彼らの横に着地する。
だが、地面にはどこから拾ってきたのか鈍色の両刃剣がざっくり刺さっていた。
「……ユニヴェール、お前、どこから湧いて出た! それは何だ!」
「フランスからわざわざ来てやった。そしてこれは剣だ」
「俺の望んでいる答えが本当にそれだと思うか? えぇ!?」
怒鳴ると、
「先にその手をうちのメイドから離せ!」
犬歯を見せて怒鳴り返される。
「メイドに離れるように言えよ!」
ソテールは両手を掲げて無実を証明した。
それをいいことにパルティータはさらにぎゅっと締め付けてくる。
「ソテール」
ユニヴェールの紅い双眸が凍った。
「だからこれは誤解──」
「その女は確かにパルティータだが、中身はパルティータではない」
「……は?」
「知り合いの使えない仕立て屋が陛下に献上する呪いの指輪を落として、それを拾ったうちのメイドが指輪に憑いていた何者かに意識を乗っ取られた」
「……だったらその剣はますます何なんだ」
「演出」
「…………」
本来ならば、太陽が頭上にあるこの時間にヴァチカンの膝元をうろついていることに対して警告をすべきだろう。
だが、そういった苦言を並べる気力を相手から根こそぎ奪うことができることがこの男の才能だ。
ソテールがすでに色々疲れて返す言葉を失っていると、
「申し訳ありません、ヴェルトール様。自分が辛気臭い娘の姿であることをすっかり失念しておりました」
今度は下から爆弾が投げられた。
「この姿では思い出していただけないのも無理はありません。それに、貴方に初めてお会いしてから随分と月日が経ちました。名乗りもしないでいきなりなんて、驚かせてしまって申し訳ありません。わたくしは──」
申し訳ありませんと言いながら抱きついたまま一切離れようとしない女が長くなりそうな独白を始め、
「お前だな! うちの女房をたぶらしかしたのは!」
そしてそこに品のない男の声が重なった。
「…………」
いち早く声の方へ動いた吸血鬼の半眼を追うように振り返る。
背後にいた不必要に肩をいからせた中年男の指が自身を指していると認識してから、ソテールは自分にもフリードやマスカーニの風邪がうつっていて今すぐぶっ倒れればいいのにと思った。そもそも風邪をバラまいたのは自分だが。
「分かってるんだ、あいつはいつもお前の話をしていたからな!」
「……どちら様ですか?」
男がわめいていたのは個性のない台詞だったが、何のことを言っているのかは察しがつく。
大方、花売りの女の亭主だろう。
「あの女をどこに隠した! 早く返せ!」
大声を出しながらも手を出してこないのは、暴力では決して勝てないことを知っているからだ。
「あの女というのは、ここで花を売っていらした彼女のことですか?」
パルティータを腰にひっつけたまま、しかし自分の声音が聖人のそれに変わるのを自覚する。
「そうだよ! 書置きがあったんだ! “幸せになります”だとよ!」
着古した衣、破れたところに継もあてていないのはそうする余裕もないくらい貧しいから。けれどよく見れば新しそうな大きな汚れはなく、露わになっている手足は無骨ではあるが傷や火傷もなく、彼女の言から一応職人見習い的な立場であるらしい彼は、推測するに仕事には真面目に行っていない。
……蜂以下だ。
「私は彼女から二度、花を買いました。一度目は風邪を患った弟子のために、二度目はその風邪がうつった上司のために。それだけです」
呼吸音、肉の付き方、立っている様子、男の外見から病の片鱗はみられない。
「彼女と私の間には何もありません。彼女が真面目に働かない貴方に愛想を尽かして出て行ったんでしょう」
「嘘を付け! 聖職者が他人の女に手を出したら破門だろう! 破門!」
それを理由にして正確に断罪していったら、聖職者の数は半分以下になるかもしれない。
「……息子さんはどうしました?」
「あの女、置いて行きやがったよ! あんなガキどうしろってんだ!」
男がその場で地団太を踏む。
どうあっても掴みかかってくるような度胸はないらしい。
「…………」
彼女と睦言を交わしたことはないし、匿ってもいない。
しかし、ここで自分と出会わなかったら彼女は子どもを置いて家を出るなんて真似をすることはなかった。そういう確信はある。
ヴァチカンの中枢で聖剣を掲げる者の存在が確かになった時、「どうして私は貴族の娘に生まれなかったのかしら」という積年の淡い落胆が、僅かでも実現性のある望みに変わってしまったのだ。
貧しく生まれついて貧しく育ってきた娘が華やかな地位を得ることはまずない。けれど本当に貴族という地位の者が存在し、しかもこんなに近くにいるならば、自分が拾われる可能性だってゼロではない。
そういう望みだ。
理想を掴もうとすることと現実から目を逸らして夢を見ることは、似ているようで全く違うのだが、それは聖人の声ではなかなか伝わらない。
人間の声でひとりひとりに理解させるには時間がかかり過ぎて、そしてそれはヴェルトールの使命から逸脱する。
「…………」
ソテールが事の折り合いを探し思考の深みにはまりかけていると、
「お前の負けだよ、穀潰し」
ユニヴェールが明朗な声で口を挟んできた。
「アンタ誰だよ」
「そんなことはお前の人生に関係ないことだ」
男とソテールの目が彼に向いた途端、真昼間の吸血鬼は饒舌にしゃべり始める。
「地位も金も働く気もないそんなお前が、地位も名誉も金もあって、かつ日夜お前たちバカどものために命を削っている正義のクルースニクに対抗できるわけがなかろう。そりゃどの女だってお前よりこの男を選ぶさ。むしろお前を選ぶ奴は人を見る目が全くない。今の役立たずなお前にはガタガタ言う資格はないんだよ。胸張って俺の方があの女を幸せにできるから返せと言える人間になってから出直せ」
ちなみに、棒読みだ。
「ユニヴェール、だから彼女とは何もないと言って──」
「お嫁さんにしてくれるって言ったのに」
……最近は、人の話を遮る輩が多い。
男がユニヴェールに叩きのめされて絶句したかと思えば、今度はひっついているメイドだ。
「わたくし以外に女がいるなんて!」
腕力は大したことがないのでいくら締められても平気だが、ユニヴェールでさえ怯んでいた凄味のある無表情が嫉妬に染まった形相は、これから数日は悪夢に悩まされそうなほど怖い。
「わたくしには何年も待たなきゃ結婚してくれないって言ったのに、でもいつかしてくれるって言ったのに!」
しかも尖ったところのない彼女の声質は、甲高く張り上げられるより底に響く。
メイドに首の付け根を絞められがくがくんと揺すられて、
「お前、他人の女房をそそのかしておいて、他の女にも手を出してたのか!」
亭主に曲解で激昂され、
「だから──」
何度同じ弁解をすれば聞く耳を持つのだとソテールが少しばかり荒げた時、
「やっと追いついた! ユニヴェール、烏を遣いにするのは止めろ、通行人から変な目で見られるではないか!」
また別の女の声が割り込んできた。
そしてソレはこちらを見るや敬礼する。
「あ、隊長」
「……あぁ」
彼女はまだ籍こそパーテルの聖騎士団だが、何度もヴァチカンへ来ている。始末人としての訓練と資質の見極め、すでにデュランダルへ籍を移したシルヴァン・レネックからの引き継ぎ、などなどでだ。
「今日は見回りですか? 外でお会いするなんて珍しいですね」
見知らぬオッサンに詰め寄られ、パルティータに首を絞められ、吸血鬼に傍観されている様を特には疑問に思わなかったようで、彼女は世間話のように続けてきた。
「そういえば、こちらへの引っ越しのために整理していたら、こんなものが出てきたんです。私は母からもらって、母は祖母から受け継いで──そうやって遡ってどこまでいくのか分かりませんが、ヴェルトール家は竜の紋章だと聞いたことがあるので」
別珍の小さな袋から取り出されたのは美しく輝く金の指輪だった。沈み彫りで描かれた竜は、確かにヴェルトール家の紋章だ。
そして彼にはその指輪に覚えがあった。
「どうしてお前がこれを?」
「詳細は不明です。私は跡継ぎではないのですが、母はたぶん私が持っているのが一番良いだろうと言って渡してくれました。その時付随する歴史については説明がなかったように思います」
「これは──」
ソテールは一度ユニヴェールへ目をやり、指輪に戻した。
「シリーン・ロードンに贈った指輪だ」
吸血鬼の眉が上がり、がばっとパルティータが離れ、そして叫ぶ。
「まだ違う女がいたなんて! 信じられない! しかも指輪を贈ったって!」
婚約や結婚の契約の証に指輪を贈る習慣は大昔からある。
「わたくしに甘い言葉を囁いて、他人の奥様を唆して、それなのにもう心に決めた方は別にいたなんて、バカにしているわ! 貴方がそんな不誠実な方だったなんて、失望しました!」
メイドが身体を震わせ、両手を握り締め、両目からぽろぽろと涙──は出てこなかった。本人は泣いているつもりなのか、何度も目をこするのだが。
「ヴェルトール様の嘘つき! もう知らない!」
灰色のメイド服を翻して丘の反対側へ駆け下りてゆく。
文面だけだと可愛らしい拗ね方に見えるだろうが、なんといってもやっているのはヴァチカンさえ蹴っ飛ばす女だ。ありがちな捨て台詞が呪いの言葉に聞こえてしまう。
木立の中の道を辿り小さくなっていく彼女の姿を見送り、
「…………」
「…………」
「…………」
「お前、聖職者のくせに女を次から次へと……」
花売りの亭主が罵ることを思い出したように口を開き、
「コイツの名誉のために言っておくと、」
何を企んでかパルティータを追いかけて行こうとしないユニヴェールがそのだみ声を遮った。
「コイツは女たらしではなく、人たらしだ。女はもちろん男も誑しこむ。なんといってもお優しくてお強いからなぁ、隊長殿は」
陽の下でも苦みの欠片もない白皙は、悪魔の如きニヤニヤをのせている。
「情報と引き換えに一夜の逢瀬を願う女は数知れず、その背を追って人間の道を外れてデュランダルに入る男も数知れず。お前の奥方のようにこの男の言動を勘違いして突飛な行動に出る輩は珍しくないんだよ。だが安心しろ」
吸血鬼の笑みが深くなる。
「その男の愛が誰かひとりに向けられることはない。何があってもその男が最も優先するのは世界の秩序だ。それに勝る愛はヴェルトールには存在しない。防衛者としてのヴェルトールの冷徹さは、殺戮家のユニヴェールとは質が全く違うからな」
暗に予言されているのだ。もしフリードに魔が差したら、お前はフリードではなくヴァチカンと世界の安全を優先させる──と。
しかもそれは咎められているのではない。その選択が常に足下の影に潜んでいることを声高に指摘して、その重石が精神を蝕むのを楽しんでいるのだ。
この吸血鬼は本当に性格が悪い。
「お前さっき自分が何て言ったか覚えてるか? 名誉のために言っておくって前置きしたよな? 俺の名誉ってなんだ?」
「何て言ったかは忘れた」
「滅びろ」
「気にするな、ユニヴェールが衝動的に世界を壊したくなるのと同じ、根底に刻まれた本能の話なんだから」
春の恩恵に溢れた微睡みの時間にする話ではないし、しかも本題からズレている。
現に花売りの亭主は自分には理解できない会話が飛び交っていることに腹が立ってきたらしい。
「てめぇらペラペラペラペラうるせぇんだ! どんだけ理屈を並べやがっても、この男がうちの女房をひっかけ──ぐっ」
しかし罵声は途中で途切れた。
つかつかと近寄って行ったヴィスタロッサが男の顎に鉄拳を叩きこみ、昏倒させたのだ。
「今は私が隊長と話をしているんです」
そういえばそうだったかもしれない。
「やはりこれは隊長に関係のある品でしたか」
何事もなかったかのように金の指輪を太陽にかざし、ヴィスタロッサがほっと息をつく。
ソテールはその姿を視界に、ユニヴェールを一瞥した。
「覚えてるか」
「あぁ、覚えている」
澄ました麗人は目を細めた。
「シリーンが聖騎士に叙された祝いにお前が贈った品だ」
女の身で聖騎士になったのはあいつが初めてじゃなかったか? そう続ける吸血鬼からヴィスタロッサへと焦点を移す。
「ということは、だ。ヴィスタロッサ。お前のその名前も偽名だな? おかしいとは思ったんだ、正式な書類にも家名が記されてこないのは」
金髪に碧眼。この辺ではありふれた容姿だが、それははっきりと血の系譜を示している。
「私に本名はありません。名前も家名も必要に応じて変えていく、何者になろうとその責は自らのみが負う、それが我々です。血統を縛る記号からは自由であれ、それがシリーンの流儀なのです」
誇らしげに胸を張る始末人見習いに、ソテールは顔を覆った。
それはきっと自分たちのせいだ。シリーン・ロードン(これも偽名だが)がヴェルトール家の苦悩とユニヴェール家の悲劇を間近で見ていたからこそ、こんな変な信条を持った一族が歴史の中で暗躍することになったのだ。
「まさか三百年も経ってなぁ」
呑気な吸血鬼がしみじみと懐かしむ。
「デューイの亡霊が我々の側に表れようとはね。……過去からの鎖はなかなか切れないもんだ」
◆ ◇ ◆
気が付いたら彼女は地面とキスをしていた。
「貴女は一体何をしているんですか」
上から降ってくる声には聞き覚えはないが、その口調には覚えがあった。
「…………」
平たく言うと盛大にコケていた彼女は、そのままの姿勢で視界の前にある自分の手を確認した。
指に指輪はない。 理由は分からないが、それを確かめなければいけない気がしたのだ。
「若い女を集めている怪しい一団がローマに入り込んだと通報があって巡回に出てみれば」
意地でも自分から顔を上げるまいとコケたそのままの姿勢でいると、
「ヴァチカンへ帰ってくる気になりましたか? パルティータ」
白い手袋に包まれた手が差し出された。
大人しくその手を頼りに立ち上がる。
「いいえ」
そして灰色のメイド服に付いた砂を丁寧に落とし、永遠の都で出会った青年をようやく正視した。
初めて見る赤毛の始末人を従え、春の笑みで歴史の中に混ざり込んでいる人外。
「その指輪のせいでここに来ることになっただけよ、たぶん」
彼の外見は、穢れを許さない白に身を包んだルカ・デ・パリスだ。
フェッラーラでユニヴェールに殺された青年が目の前にいることはある意味怪奇だったが、理由は考えるまでもない。
中身には別の者が入っている。
「クロワ」
最も馴染みのある名はセバスチャン・クロワ。最近の通り名はクリスチャン・ローゼンクロイツ。そして時代を超えても変わらない名は、死の天使サマエル。
ソテール・ヴェルトールやシャルロ・ド・ユニヴェールがかつて必死で追っていたという聖なる魔物は、彼女が生まれてからヴァチカンを出奔するまでの長い間、執事として彼女の傍らにいた。
彼女以外のほとんどの人間にその姿を見せたことはなかったようだが、物心つく前に父が死に母が祖国へ帰った彼女にとって、この堕天が親代わりだったと言っても過言ではない。
それが今度は、文字通り人間の皮を被って聖なる一団を率いているらしい。
「ユーリス・ロバンは元気?」
「もちろん。噂を聞いていませんか? 彼は最近カプラに立ち寄ったらしいんですが」
「流行病で随分たくさんの人が亡くなったそうね」
「病では、仕方ありませんね。生贄の奪還に尽力されたマルグリット皇女も悲しまれたでしょうに」
かつて黒尽くめだった執事が、今は眩しく漂白された衣装で微笑む。
包帯の下に憎悪の傷を抱えていた双眸は、淡い翠玉の色をたたえている。
きっと、本物のルカ・デ・パリスが見てきた追想の景色は、この天使の持つ存在感の前に儚く霧散してしまったに違いない。
「……貴女、自分から帰ってくる気はありませんか?」
「ありません」
指輪は、彼の手の中で遊ばれていた。
「貴女の父親であるフォリアと貴女の母であるパレストリーナが婚礼を挙げた時、私はあの男に約束させられました。当初の契約とは別にね」
パルティータの執事だったクロワだが、契約を交わしていたのはパルティータの父だ。 聖なる血筋と謳われながら、血は争えない。 片や幽閉されたまま堕天と取引し、片や牢壁を破って吸血鬼の小間使いをやっているとは。
「まだカリストゥス三世が教皇座にいた頃です。いたとは言っても死にかけていましたけど」
市街からは外れているのか、比較的広い道だが人通りはない。 誰も通りかからない道の脇で、黄色い花をいっぱいにつけたミモザの木が風に揺れている。
「“もし子どもが生まれたら、再びボルジアが司教冠を載せるまで自由にさせること”。それがフォリアとの約束です」
私はそもそも貴女の母親がヴァチカンに足を踏み入れることを快く思っていませんでしたし、子どもが生まれたら即呪い殺すと思っていたのかもしれませんね、そう続けた死の天使に、
「まさか。授かるかも分からない子どもの命を案じるような、そんな他人想いの人間じゃないでしょう、父は」
パルティータは首を振ることすらせずに返した。
クロワの視線は遮られることもなく逸らされることもなく、ひとつ大きく瞬く。
「えぇ、そうですね。あの人はとても自分本位な暴君でした」
「みんなそう言ってたもの」
公理によれば、悪魔と取引するためには代償が必要なはずだ。様々な口から語られる父の姿を想像するだに、身を削って身内を救おうとするタイプの人間ではないのである。何を代償に約束を交わしたのかは知らないが。
「彼は確かに暴君ではありましたが──優秀な未来視でした」
「未来視?」
「枢機卿からはそう言われていましたよ。彼が未来について語ったことは大抵当たりましたから。けれど神から言葉を授かっていたわけではないようなので、預言者ではないというわけです」
「……それが?」
どこからか、薄いピンクの花びらがひらひらと舞ってきた。
近くにアーモンドの木があるのかもしれない。
「でも彼の占いは詐欺みたいなものでした。彼は未来を視ていたのではなく、自身が語ったことを片っ端から実現させていただけなんですから。人を困らせることに対する彼の悪賢さは恐ろしいほどで、幽閉なんて障害にもなりませんでしたよ」
天使はくつくつと喉を鳴らして笑う。
「彼のやることの大半には彼の利益に繋がる何らかの意味がある。貴女に一定の期間自由を与えたことにも彼の計算があるのかもしれませんね」
当時からボルジアが再び返り咲くことを確信していたのなら大したものです、そう感心するクロワの言葉を追ってまた数枚の花びらが青い空に吸い込まれていった。
「でも貴方は私がヴァチカンを出る時に邪魔をしたわ」
「当然です。貴女はこちら側にいなければいけない。フォリアと私が引いた線の内側にいなければいけないのです」
「それは私のため? 貴方のため?」
「両方です」
「ふーん」
「出て行ったものは仕方がない。そう考えることにして我々は今まで貴女に手を出しませんでした。フォリアはおそらくそうなることさえ分かっていたでしょうし、第一逃げ込んだ先がユニヴェール邸とあっては無策では分が悪い」
土色の街の中に青い空が切り取られ、狩人とメイドの頭上に広げられている。
春の訪れを全身で叫びたくなるような、蒼空。
「フォリアの意志はまだ強固に生きています。そしてその意志はついに組織を手に入れました」
人間と取引をした悪魔や魔物は、さっさと終わらせて報酬をもらって自由になりたいと考えている輩が多いと聞く。しかし昔からクロワの口調には、フォリアとの契約が本人が死んでなお続くことに対しての苛立ちは含まれていなかった。
「貴女の主と私の主の理想郷は根本から相容れません」
──そうだ。彼は悪魔でも魔物でもなく、天使だ。いつもあまりにも腹黒く嫌味ったらしいから忘れていた。
「人々は、幸福な平穏と先の見えない混沌と、どちらを選ぶでしょうか」
「前者を選んだら吸血鬼が世界を消し飛ばすかも。つまらないって言って」
クロワの明るい双眸に、そんなことは想定の範囲内だという高飛車な笑みが浮かべられた。そしてそれは留まることなく昏い色に変貌する。
「ユニヴェールは脆弱なすべてを壊そうとする。ヴェルトールは身を賭して暗黒都市とユニヴェールに対する盾になろうとする。けれどその戦いの足下、痛みを抱えた迷える子羊に安住の地はないのです」
「貴方は相当頑丈な羊小屋を作るつもりね。せいぜい頑張って」
パルティータはクロワの据えた眼差しを軽く払いのけ、小さく肩をすくめた。
か弱い人間のためにデュランダルに入って粉骨砕身働くとは、なんとも素晴らしい心がけだ。多くの人々を救いに救って、これでもかというくらい甘やかすつもりらしい。どうせなら菓子職人に弟子入りでもしてお菓子の小屋を作ればいいのに。
この天使は盲目だから見えていない。
過ぎた愛は毒だ。
……まさかそれがフォリアとの取引内容でもあるまい。皆から人間である方がおかしいと評される人でなしが、人々の幸せを願っていたとは到底思えない。
「キルケがローマ帝国の再興に執着するのなら、ますます混迷は深まり、戦禍は大きくなり、民も国も世界そのものが疲弊するでしょう。その前に貴女にはこちらに戻ってもらわないと」
一体、フォリアとサマエルはそれぞれ何を目的に何を代償に、契約を結んだのか。
ヴァチカンにいた頃様々な角度から探りを入れたことはあるが、クロワにはいつもはぐらかされていた。
今では万策尽きて知ろうという気も起きない。
「──隊長」
クロワの背景に徹していた赤毛の男──おそらくはアスカロンがカプラで遭遇したという新人始末人、ヴェルトロ・レンツィ──が、何かを気にして空を斜めに見上げた。
彼がいても憚ることなく昔話をしているということは、この赤毛は始末人の中でもパリスがフェッラーラのパリスでないことを知っている者ということになる。
教皇領よりもフランスの海岸の方が似合いの明るく穏やかな風貌。それは一見無害そうだが、デュランダルにはまともな人間がいないというのが定説だ。何を隠しているか分かったものではない。
「ユニヴェール卿がローマに留まったままです」
「今は放っておいて大丈夫です、きっとパルティータを追ってきただけですよ。彼は派手好きですから、つまらない時機につまらない闘いはしません」
この天使の凪のような声が、口調が、一度だけ変わった日のことは忘れていない。
パルティータがヴァチカンの壁を越えた日。
「というわけで貴女たちをもてなす準備はまるでありませんからね、今日は無理はしません。用事を済ませてさっさとパーテルへ帰ることです」
「ありがとう。ついでに指輪を返して」
パルティータが片手を突きつけると、クロワが眉間を寄せる。
「これですか? 構いませんが……絶対にはめないでくださいね」
……もう遅い。
「そうだ。ひとつだけ、訊いてもいいですか?」
掌に指輪を載せながら、否と答えても続けてくるくせに律儀に伺いを立ててくる。
「どうぞ」
「ミトラもカリスも訊きたがっているはずです。そして私も知りたい」
こちらを見据えてくる碧眼の奥に、焼かれた双眸が映る。包帯を変える時だけしか露わにはしなかった、彼が忌み嫌う傷痕。
「貴女は何故、多大な犠牲を払ってまでヴァチカンを出たのです」
「…………」
世界から、音が消える。
ローマの春から、色が消える。
白と黒の鮮やかな過去が二者の脳裏に入り込む。
「きっと、枢機卿たちはその答えを知ってる。彼らは正直じゃないから語らないとは思うけど」
「……枢機卿が?」
クロワの顔に困惑が浮かんだ。それは、とてもとても貴重な、この天使が無意識に見せる素直な感情だった。
「昔、貴方たちは何度私を助けた?」
あの頃は、二匹の護衛がいた。黒の執事セバスチャン・クロワ、蒼の吸血鬼フニャディ・ラースロー。
「……何度も」
「そう、何度も」
二匹の護衛がいてさえ、何度も。
「貴方たちは常に理想を追う。私たちは常に現実と闘う。答えが分からないのは、その違いが原因」
クロワ、ソテール・ヴェルトール、デュランダル、……ユニヴェールも三使徒もそうだ。彼らは理想を唱えて理想を追って力技でそれを実現しようとするだけの根拠を持っている。
だが、ほとんどの人間はそんな突拍子もない能力は持っていないし、可能性を感じられることさえ少ない。
それはパルティータも同じだ。彼女は血統書こそ持ってはいるが、それは諸刃の剣であって、しかも簡単に崩れ去る砂上の楼閣でもある。必要だからこそ欲しがられているだけで、無条件に崇め奉られているわけではないのだ。
現に、オルレアンの乙女の顛末は、その事実をあからさまに示した。
「でもその違いは貴方のせいではないし、ミトラのせいでもない」
それを理解したのはいつ頃だっただろう。
クロワは父フォリアとの契約が終われば彼女の下を去る。
デュランダルは大義を優先する。
“セーニ”が大きな意味を持つ限り、その存在を消そうとする者と取り込もうとする者が現れる。
“セーニ”が大した意味を持たなくなれば、教会も人々も手の平を返して彼女を棄て、忘れ去る。
破滅か衰亡か、そこにあるものが何にしろ、白い牢獄の中で安穏と暮らすことは、ぽっかり開いた穴へゆっくりと転がり落ちていくことに等しい。
それを運命と受け入れる生き方もあるだろう。或いは、クロワが創りたいらしい幸福だけの楽園の完成を待つのも手だろう。
だがセーニの矜持はそれを良しとはしなかった。生き延びることに執念を燃やす枢機卿たちの最たる者がセーニなのだから、当然と言えば当然だ。
もちろん彼女がヴァチカンを出た理由はひとつだけではない。複数の事情を当時の彼女が彼女なりに考えた結果だったが──
「…………」
クロワが黙り込んだのは、提示されたヒントから答えをじっと考えていたために違いない。
でも天使が困っているのは楽しいので、答えはひとつも教えない。
「いずれにせよ──」
しばし時を置いて視線を上げてきたクロワの顔は開き直っていた。この男にとってこの疑問は純粋な疑問であって、それ以上のものではないのだ。答えが分からないのは気持ちが悪いが、機微を深く研究するほどのことではない、その程度だ。
「遊びの時間は終わりです」
「私は常に仕事をしています」
「貴女のすべきことは吸血鬼の小間使いではありません」
「…………」
ここで反論するとまた小言が振り出しに戻ることを予感して、パルティータは口を閉じた。
「貴女はきっと、最後にはこちらに戻っていますよ」
言い置いて近付いてくるクロワの碧眼は疑いなくそれを確信していた。人々の誕生日は毎年同じ日に訪れる、そんな自明の確かさだった。
人間にも魔物にもできない狂信的な白亜の眼差し。
気付いたのはいつ頃だっただろう。
この死の天使は民のこともパルティータのことも、契約を交わしたフォリアのことすら見てはいないのだ。あの閉ざされた両眼が見ているのは、己を追放した主人それだけだ。
神が望むなら、神が望むように。
それ以外、この男は自身に存在意義を与えていない。
それはつまり、神が望めばもう一度地上のすべてを洗い流すことすら厭わないということでもある。
「私は──」
すれ違うところまで来て足を止めたクロワが、アルカイックな笑みを浮かべて耳元で囁いてくる。
「そこにあるのが貴女の柩であっても構わないんです」
「…………」
「必要なのは貴女であって、それが動いていようといまいとどちらでもいい」
「…………」
パルティータが真っ直ぐ前、閑散とした通りを見つめて
「やれるもんならやってみれば──」
口を開けば、
「そうそう、いつまでも主人面しないでくださいね」
同時に遮られる。
「私には新しく仕える方がいるんです。故あって今は彼女のお傍にはいられませんが」
男の声に僅かの優越と劣等、相反する色が滲んだ。
主に逃げられた執事がその主を見限り、新しい主を迎える。事象としてはさして珍しいことでもない。
「貴女と違って、真摯に哀れな世界を憂う素晴らしい方ですよ」
「……人間?」
「えぇ」
「そう」
メイドの変化のない顔貌にほんの一瞬だけ微笑が過ぎる。
「私の柩がそっちに凱旋する時が楽しみね。それは貴方がユニヴェール卿を滅ぼした栄光の日でもあるはずだから」
吸血鬼の名で、クロワの柳眉が寄る。
パルティータ自身も口の中に苦味を感じ、息をついた。
どうせひとりでは何もできないくせにと嘲笑われるのが嫌なのだ。実際そのとおりなのだが、一度表層に出てきた感情はどうにも御しがたい。
「じゃあ、そうなることを楽しみにしています」
平坦にそれだけ告げると、パルティータは佇むクロワを残してその場を後にした。
そして、数歩行ったところで立ち止まる。
バカにされるだろうから元執事には訊けなかった疑問を赤毛の始末人に問うために。
「ねぇ。ここはほんとにローマなの? 私はさっきまでパーテルにいたんだけど」
◆ ◇ ◆
「ローマ中を探せ。怪しい奴らが若い女を集めている可能性がある」
「フランスから連れてこられた方々は全員我々が保護したのですよね? 獲物をすべて逃がすなんて失敗をしたら、普通に考えて賊は諦めるのでは? 少なくとも場所は変えるでしょう」
「いえ、それがご婦人方の話を総合すると我々が保護したのは馬車に乗せられていた全員ではないようなのです。何人か姿のない方がいるそうで」
「どさくさに紛れてローマ市民に紛れるつもりということですか?」
「自ら賊の下に戻った可能性もある」
ソテールの言葉に、テーブルに集まった聖騎士たちが困惑の色を見せる。
「ヴェルトール隊長、それは……どういう意味ですか?」
「彼女たちの中にはまだ賊の言葉を信じている者がいる、そういうことだ。未だに貴族の愛人にしてもらえると思っている娘は、保護するために来た我々の方を敵だとみなしただろう。賊は空想的な明るい未来を用意してくれている、一方で我々は現実の生活に引き戻そうとする」
長い間虐げられてきた者たちは、目の前に吊られた幸せの糸をそう簡単に放しはしない。
「依頼主が魔物で、娘の人数が重要だった場合、賊は何としてでも逃げられた分を取り戻そうとするはずだ。魔物との契約違反は死を意味するからな」
ソテールの蒼眸がテーブルの上に広げられた地図に落とされ、聖騎士たちの視線も自然それを追う。
本来ならば、ソテール・ヴェルトールというのは聖騎士の身分で言葉を交わすこともできないような人間だ。稀に巡警の際に会っても敬礼を交わすか短い儀礼的な言葉を交わすだけで、同じテーブルを囲むことなどまずあり得ないし、ましてこうして共に対応を協議するなんてことはそれこそ空想的な事態だ。
「だから危険を承知でローマで娘を集めようとする可能性が高い……というわけですか」
「どうせ集めるなら大きな都市の方がやりやすいもんな」
いつになく前向きな聖騎士たちを前に、ソテールは付け加えた。
「しかしパーテルと同時にローマでもすでに女を集めていた可能性もある。ヴィスタロッサが聞き込みにまわっているが、すでに一件、不自然な失踪が起きている」
偶像化されたクルースニクの長。その正妻に想いを馳せていた花売りの姿を言葉に重ねながら。
「依頼主が人間でも魔物でも構いませんよ、ローマの聖騎士団が侮られていることには変わりません」
「絶対見つけないと」
ローマの聖騎士詰所に沈黙が満ちる。
暗澹と緊張と高揚が混じった沈黙だ。
ソテールは彼らがさらわれた貧しい娘たちよりも騎士の名誉を優先したことには敢えて触れず、地図上の何ヶ所かを順番に指した。
「奴らはパーテル周辺で孤児院をまわって娘たちを集めていたらしい。ローマでもまず孤児院をあたれ。そして露店商。それから同業者、乗合馬車の御者だ。縄張りに煩い連中は不審な奴をよく覚えている」
「了解しました!」
「本格的に雨が降る前に捜し出せ」
『はい!』
陽が傾くや空は翳った。
抜けるような青だった天上は今や灰色の雨雲に覆われていて、遠くから春雷の轟きが聞こえてきている。
雨が本降りになったら目撃証言は取りにくくなるだろう。
ばたばたと階段を駆け下り街中へ散っていく聖騎士たちを見送ってから、ソテールは詰所の屋上に出た。
昼間の穏やかさは白昼夢だと言わんばかりに、気温は下がり吹き荒ぶ風は頬に冷たい。刻々と夜へ落ちてゆく空気の濃さのせいで、ローマ全体が不気味な不安に覆われていた。剣呑な気配がいくつも点在し、複雑に絡んで溶け合っている。
焦燥、諦め、嘆き、怒り、混乱──。
頬にひとつふたつ滴りが当たって視線の方向を変えると、
「あれは……」
少し先の建物の影にパルティータ・インフィーネが雨を避けるように立っていた。
虚空の一点を見つめて表情が固定されている様子を見るに、指輪は外れたのだろう。意識を乗っ取られていた時の記憶があるのかないのか、ないのだとしたら、いきなりローマに放り出されて途方に暮れているのかもしれない。
常人であれば衛兵か役人か聖騎士に助けを求めるのだろうが、ヴァチカンを出奔した身である彼女がそれを選択肢に入れているとは思えないからだ。
曇天が霧雨に変わり、ローマの街が暗く煙り始める。視界があるうちに天候が回復する見込みはなさそうだった。
「しょうがない、回収に行くか」
ソテールが肩を落としたと同時、路地の向こうから陽炎の如く黒い吸血鬼が現れた。
湿った靴音が界隈に響き、主が迎えに来たことに気付いているだろうに、しかしメイドは微動だにしない。
息を潜めて成り行きを見ていると、眼前を烏の群れが騒ぎながら横切って行った。
目を戻せば、ユニヴェールとパルティータが何言か交わしている。彼女の手から何かがユニヴェールに渡り、それでもメイドは主へと目をやることもなく、じっとどこかを睨みつけていた。
おそらく烏は吸血鬼の伝令だったのだろう、しばらくして黒塗りの馬車が彼らを拾いにやってきた。
そしてふいにユニヴェールが顔を上げた。
嗤った紅と目が合う。
彼は片手を掲げ、小さく輝くものを弾き飛ばした。
──呪いの指輪。
「あのバカ、誰かが拾ったらどうするんだ!」
そうでなくてもローマには物乞いや盗人が多い。あんな輝石が転がっていたらすぐに持ち去られてしまう。
これ以上の面倒事はごめんだ。
慌てて踵を返し、白衣を翻して現場に急行すると、案の定すでに馬車は影も形もなく、指輪だけが土に塗れて濡れていた。
拾い上げると、背後から大きな声がした。
「ヴェルトール隊長、……あ、指輪。パルティータから外れたんですね」
「ヴィスタロッサ」
「良かった。無事なら会う機会、ありますから」
彼女の声はよく通る。ともすれば悲観に傾く人の心を一掃する声音だ。
「呪いの主に随分気に入られていたようですが、隊長にお心当たりは?」
ニヤニヤするのはやめてほしいが。
「今回と同じような事件だ。入れ知恵をしたのは魔物だったが、主犯は人間だった。悪趣味な輩で口減らしの子どもや浮浪児を言葉巧みに集めては──彼女もその中のひとりだったが、我々が真相に辿りついた時にはもう遅かった」
死に際の少女からの、“求婚”というにはあまりに幼い言葉を、無碍にはできなかったのだ。
ユニヴェールが置いていったとおり、この指輪は自分が持っているべきなのだろう。
「では今度は遅くならないように早急に捕まえましょう」
ヴィスタロッサが片手で拳を握る。
「件の花売りの目撃がありました。やはり馬車に乗ったようです。ただし、乗せた男は賊ではなく、それなりの身なりをしていたとか。ローマに仲介役がいるってことですよね?」
「だろうな。利に群がる輩はどこにでもいる」
「では、いざ行かん!」
「まぁ待て」
ソテールは、勢い込んでくるりと身体を反転させた女始末人の襟首を掴む。
「迅速な行動は評価するが、無策はダメだ」
かつて、ソテール・ヴェルトールとシャルロ・ド・ユニヴェールが共に白い聖なる衣をまとっていた時代、リカード・デューイという聖騎士見習いが任務に同行することが度々あった。
背中を預けて戦える程に技量の相性はいい二匹のクルースニクだったが、個々が抱える世界観は対立しており、少なくない頻度で現実的な衝突にまで発展したため、デューイはその緩衝剤として投入されたのだ。
上の期待以上の働きを見せた彼が、実は強い動機を持って聖騎士隊に紛れ込んだ“彼女”であったなど、誰が想像しただろう。
しかしそれが暴かれた時にはもう、彼女には十分過ぎるほどの功績が積み上がっていた。
公式的な本名はシリーン・ロードン。聖騎士隊での名はリカード・デューイ。彼女は歴史上初めて、女の身で聖騎士に叙された人間となった。
「でもパリス隊長たちも巡警に出ているそうですよ。あっちが先に見つけちゃったらどうします?」
「どっちが先に見つけたっていいんだよ。見つかれば」
デューイの末裔だというヴィスタロッサをずりずりと引っ張りながら、ソテールはふと別の可能性を思い付いた。
当たり前に存在しすぎていて深く気にすることはなかったが、よく考えれば不自然な地位にいる人物がヴァチカンにはもうひとりいるのだ。
デューイやヴィスタロッサと同じ、金髪碧眼の女が。
「何故私を呼ばない。少し指先を切れば済むことだろう」
「……あぁ、忘れていました」
夕闇が近付く霧雨の街角で、メイドは黙して雨宿りをしていた。
指輪をしているならどこへ飛んで行こうと最終的にはソテールのところへ戻るだろうと高を括っていたのだが、指輪が外れているということは想定していなかった。
しかも転んで外れるとは……どこの三流戯曲だ。
「どうやって安全にパーテルへ帰ろうか思案していたところです」
メイドはユニヴェールが近づいても正面を向いたままだった。
「すぐに馬車が来る。指輪は持っているか?」
「はい」
ブラウボイレンの青い泉を思わせるその石は、灰色の世界でも悲哀の輝きを放っていた。
この指輪を呪いの指輪に変えている嘆きの主については、ソテールと見解が一致した。
はるか昔、クルースニク時代にいくつも残してきた禍根のひとつだ。
お優しい隊長殿は死にゆく者たちの願いをひとつでも多く叶えようとする。ユニヴェールはそれを偽善だと言って糾弾して、いつもデューイが間に立ってすべては時と場合によるものだと双方を宥めた。
他人に迷惑がかかる場合にはソテールが叱責され、ソテールの博愛が必要とされる場合にはユニヴェールが口を塞がれた。
「道で転んでいたら、クロワに会いました」
回顧はパルティータの言葉で打ち切られる。
「クロワ……サマエルか?」
「パリスの皮を被って立派にデュランダルの隊長を務めていました」
ユニヴェールの疑問形を無視して、抑揚のない報告は続く。
「アスカロンから報告のあった新入りのデュランダル、ヴェルトロ・レンツィは、少なくともパリスがパリスでないことを知っています」
伏せられている睫毛のせいで、パルティータの目に映る感情を読み取ることはできない。
「クロワは、キルケがローマ帝国の再興を狙っていることを知っていました。何故でしょう」
「奴の情報網が飛びぬけているか、内通者がいるか──」
「彼は私の執事でしたが、今は別の主がいるそうです。アスカロンの教会からデッラ・ローヴェレ枢機卿が連れて行った少女が現在の主である可能性が高いと思われます」
「聖女カタリナか。……理由は」
「クロワが“彼女”という代名詞を使ったこと、“今はお傍にはいられない”と言っていたこと。ローヴェレ枢機卿がパリに逃れていることを鑑みれば、合致します。そしてローヴェレ枢機卿を匿っているフランスの動向。シャルル八世はナポリを狙って侵攻を企んでいるようですが、何らかの後ろ盾がなければ行動を起こすことはできないはずです」
「デッラ・ローヴェレとカタリナを通じてサマエルが背後にいるからこそフランスが強行な態度を取っている? ありえなくはないが──結論が先になっていないか?」
「それを調べるのが貴方の仕事でしょう」
低く抑えられたその言葉に、ようやく気が付く。
ユニヴェールの記憶が彼が仕えたインノケンティウス三世の輪郭をなぞり、目の前の娘に重ね合わせる。
これは勘気だ。
サマエルの何かがパルティータの水平な感情を苛立たせたのだ。と悟ると同時に、その波を起こすことのできたサマエルに対する苛立ちが湧く。
「そこまで言うなら調べておくが」
暗黒都市からの馬車が迎えにやって来たので、数区画先の屋上からこちらを見下ろしているソテールに対して指輪を放ってやる。
始末人が慌てふためいているうちに、
「パーテルの屋敷へ戻れ」
御者に告げ、パルティータを馬車に押し込みローマを発った。
◆ ◇ ◆
「何があった」
帰路、フランス領へ入っても押し黙り続けるメイドに、ユニヴェールはようやく訊いた。
不機嫌になると黙るのがこの家系の習性なのか、かつてインノケンティウスにも全く同じ台詞を何度も言った覚えがある。
だが返ってきた反応は過去とは全く違うものだった。
「クロワにバカにされたのです」
闇の帳が降りた外を眺めたまま、メイドの唇には尊大な笑みがのる。
「あの分からず屋の執事は、人間をナメています」
口調は落ちついていて緩やかだが、選ばれているフレーズは鋭利だ。
サマエルはパルティータがヴァチカンにいた時分、それこそ生まれた時から出奔するまでの間、彼女の世話と保護をしていたということだけ聞いている。
それが実際にはどれほどの強度の鎖で繋がれた関係だったのか、ユニヴェールには推しても知ることはできない。
再び微かな苛立ちを喉元に感じ、吸血鬼は目を細めた。
「殺せるものなら、殺してみればいいのです」
仄昏く言い放つヴァチカンの聖女の手を取ろうとして、止める。
その言葉はまるで“ユニヴェール”から世界を護るための防波堤のように響いたからだ。
セーニの聡さは三百年前から知っている。己が世界と戦ってさえいればこの男は暴挙には出ない、そういう打算があっても驚きはしない。
しかしすぐに思い直す。
──だったら何だというんだ?
「私を呼べばよかったのだ。サマエルに会った時すぐに、お前の血で」
ユニヴェールは背を預け直し、足を組み替えた。
「助けの呼び方は知っていると、お前の口から聞いた記憶があるが?」
「…………」
おそらくこの娘はとうの昔に生きることに対して腹を括っている。
それはもはや死人であるユニヴェールには手の届かない精彩だ。
「呼びつけられたからといって料金は取らんよ」
だがセーニには欠点もあって、強情過ぎる矜持がしばしば彼ら自身の首を絞めてきた。
インノケンティウスは最期に敬虔な信徒であろうとするあまり、吸血鬼ユニヴェールを滅ぼす瞬間を逃したし、パルティータもクロワに対するおかしな意地のせいで、自分が危なかったことにも気付いていない。
始末人二人に囲まれて、抜剣されたらどうするつもりだったのか。
すりこぎでいい勝負ができたら、今度こそこいつを人間とは認めない。
ユニヴェールは窓枠に頬杖をつき、パルティータとは反対側の夜闇へと目をやった。
「お前がパーテルの屋敷の扉を叩いた時から、私はお前の盾で槍だ。使うことに何かを感じる必要はない」
「…………」
さっきから返事が全くないので吸血鬼はメイドの方へ視線を流し、
「…………」
勢いよく身を起こした。
「相手がしゃべっている時に寝るなーッ!」
THE END
「ねぇ、ユニヴェール卿! 私が陛下に献上せねばならない指輪はどうなったんですか?」
「失くした」
Back Menu
Home
BGM by Thomas Bergersen [Rada] City Of The Fallen [Throne of Divinity] Delain [Come Closer]
Copyright(C)2013 Fuji-Kaori all rights reserved.
|