第23話 スリープレスナイト
前編
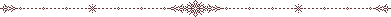
昏く空っぽの城の中を足音が徘徊する。
足下からはか細いすすり泣きが聞こえ、かざす燭台の炎が照らしだすのは、背筋を伸ばし椅子に腰かけたまま動かない屍の姿だ。
魔物の証であるその紅の瞳には、もう偽りの生すら宿ってはいない。
城には、ソレを含めふたつの屍があった。
もっとたくさん棲んでいたはずだが、体力が続かず先に死んだ仲間は自分たちの手で燃やしたのだろう。しかし時が経つにつれてそれもできないほど衰弱し──最後まで生き延びた二匹は誰に燃やされることもなく、こうして死骸が残ったに違いない。
男は派手な裏地の外套を肩にひっかけ直し、城の一番高い場所にあるバルコニーへ出た。
蒼白い霧が海のように広がる山と湖。
肌を刺す寒さに支配された、眠りの森。
「存在するはずがなく、しかしここにあるものは何だ」
やる気のない問いかけは誰に向けられたものでもない。すべて独り言だ。
「答えは──吸血鬼の死体」
灰にならなかった、魔物の抜け殻。
「…………」
眼下で、雲になりきれない水の粒たちが湖をゆっくりと渡ってゆく。
「では、誰が、何のために、どうやって彼らを殺したのでしょーか」
答えは誰にとって必要なのか。
狩る者か、捧げられた者か、狩られる者か、傍観する者か。
いと高き神か、聖なる使徒か、蔓延る人間か、夜に棲む者か。
遠く、この地に来たる複数の馬車の音を聞きながら、近く、息を潜める白の気配を捉えながら、彼は頬杖をついて蒼い樹海の目覚めを待つ。
◆ ◇ ◆
二頭の青毛に引かれた黒塗りの馬車が、軽快な音を立てて小刻みに揺れながら、木立の脇のなだらかな上り坂を行く。
景色にはまだ彩りがなく、三歩進んだ春から二歩退がった外界には、白い残雪こそないものの味気ない薄茶色の叢林が広がっている。
春に浮かれて暖炉を掃除してしまった者たちが、どんよりとした寒空を見上げて舌打ちするのが聞こえる。反対に薪売りは在庫が消えて胸を撫で下ろしていることだろう。
そんな詩的な感想を胸にしたまま、アスカロンは自分の前にある現実をもう一度直視した。
パリで拾った優男とシャムシールが、かご一杯のゴーフルに蜂蜜をつけながらひたすら食べている。バリバリと規則正しく無機質な音を立てて。
「いい加減にしろよ」
何度目かの注意を半眼ですると、
「だって美味しいんだもん。やっぱりド田舎のパーテルで売ってるやつとはちがうよね、パリのお菓子はさ」
シャムシールはこちらを小馬鹿にした半笑いで生意気な内容を返してくる。
春仕様だとかいって、少しだけ色を浅くした若草色の法衣にくるまって。
「太って子豚になっても知らねェからな」
「今までなったことないもん」
「滅亡した国の元首はみんなそう言ったんだぜ」
「聞いたの?」
「……聞いたわけねぇだろ」
「じゃあ、みんなそう言ったかどうかはわかんないじゃん。子ども相手だからって嘘言わないでよ」
「オ・マ・エはーーー!」
「まぁまぁまぁ」
アスカロンがシャムシールの首根っこを捕まえようとすると、少年の横で揺られていた優男が、ゴーフルを片手に、もう片方の手をひらひらさせて割って入ってきた。
彼は名をメリル・ジズ・メムといい、ユニヴェール行きつけの怪しい仕立て屋の怪しい店主である。
「旅は楽しむのが一番なんだから、お説教は帰ってからでいいじゃない。ねぇ?」
「そうそう、ホントに無粋だよねー。せっかくの遠足なのに」
「遠足じゃねぇよ」
パリの裏通りにある彼の店は夜中しか営業しておらず、商売相手は化け物のみ。扱っているものも地獄の河を織った外套だのバビロンの空中庭園に咲き乱れる花の香を織ったドレスだの珍品ぞろいだし、もちろん本人もまっとうな人間ではない。
「しかもなんで俺がアンタの護衛もしなきゃならないんだよ」
長年パリに棲みついていると言いながら、その男は全身にオリエントの風をまとっている。
ゆるいクセっ毛の黒髪の下の肌は褐色がかり、猫のような金色の双眸には商人らしい人当たりの良さと抜け目のなさが交互に過ぎる。
首には幾重にも連なる金鎖、肘まである黒のフィンガーレスグローブの中指に繋がっているのはガーネットの指輪、腰には船乗りや海賊たちが愛する舶刀。
普段店に立っている時の控え目さとはうって変わり、ご存分に羽を伸ばして旅を満喫していらっしゃるようだ。
「行き先が同じなんだから頼まれておくれよ。僕は自分で仕入れをしなきゃ成り立たない商売だからねぇ。店でボーっとしてたって並べられるような珍しい生地を誰かが持ってきてくれるわけじゃないから」
「ふーん」
行き先──それはパリをずっと過ぎた山奥にある町だ。
アスカロンとシャムシールはその町の城主にユニヴェールからの手紙を運んでおり、たまたまパリで行き会ったメリル・ジズ・メムにそっちに用事があるから乗せくれとガリアのお菓子をちらつかせながら頼まれ、二つ返事でシャムシールが承諾した、というのが現状。
「テンチョーのとこって面白いものたくさんあるよね。全部テンチョーが作ってるの?」
シャムシールは彼のことをテンチョーと呼ぶ。アスカロンは店長と強制されている。ユニヴェールはメムと呼ぶ。
「仕立ててるのは僕じゃないけど、糸は全部僕が仕入れてるの」
「地図だとパーテルよりも辺鄙な町に思えるぜ、そんなところにアンタの興味を引くような代物があるのかね?」
アスカロンが深い意味は含ませずに問うと、砂漠の砂のような菓子屑を口元からぬぐい、異界の店長が低く笑う。
「……あるんだってさ」
山間の荒野に、一陣の潮風が吹いた。
◆ ◇ ◆
カプラ。その町は、葉を落とした山々の合間にあることに加え、聖地へ向かう巡礼路からも外れていて旅人の姿がないせいか、閉じた世界を感じさせた。
薔薇の花園で囲まれた囚われの城とはまた違う、それひとつで完結している共同体。新しい流れが入ることを嫌い、循環する時間の中でつつがなく一生を終えることを望む人々の世界。
貧しく、けれど抜きんでて富める者もなく、細々とした不平不満はあるが武器を取るほどでもない……。
「ご迷惑ではありませんでしたか?」
「いえ、とんでもございません。姫君にご逗留いただくなどこれ以上ない名誉でございます。こちらこそ、領主や町の代表が不在にしておりご挨拶に上がれず申し訳ありません」
恐縮にもほどがある浮かない顔。
上司の不在が心苦しいというより客人の相手が憂鬱だ、というのがあからさまだ。
大人なら苦笑して受け流すかもしれないが、マルグリット・ドートリッシュはそれを声に出した。
「もはやフランスとは関係のない私の受け入れを承諾したことで、フランスから嫌味でも言われましたか?」
「そんな滅相もない! 姫君を丁重におもてなしするようにと陛下直々のご命令があったほどですよ」
「……それが嫌味だわ」
少女は、誰にも聞こえないようにため息をついた。
事情を知っている者は皆、忍んで笑っている気がする。
同情や憐憫や嘲笑や、そこに含まれる感情は多々あるだろうが、あれが王妃の位を追われた皇帝の娘かと思われていることだけは確かだと感じてしまう。
彼女の──マルグリット・ドートリッシュの父は神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン一世で、彼女は幼い頃からフランス国王シャルル八世の王妃になることが決まっていた。
そのためにずっと、悠然と流れるロワール川を見下ろすアンボワーズ城でシャルルの姉であるアンヌ・ド・ボージューの教育を受けてきたのだ。蝶よ花よと不自由なく育てられ、アンボワーズの人々も自分の娘のように可愛がってくれ、始まりが政略結婚であったこと以外は幸せを絵に描いたようなこれまでだった。
しかし世界を巡る風向きは気まぐれで、アンヌ・ド・ボージューはそれを嗅ぎ分ける天才で、夫となるはずだったシャルルは彼女にとっては望むほど騎士ではなくて、急転直下、フランス国王は姉の命令でブルターニュ公国の女公アンヌ・ド・ブルターニュとの結婚を強行したのである。
つまりは、マルグリットはいとも簡単にフランス王妃という地位から追い出されたのだ。
今はようやく形式的なゴタゴタが落ち着いて、フランスに背を向けフランドルへ戻る旅路というわけだ。
もうアンヌ・ド・ボージューを恨みもしないし、是が非でもシャルル八世の王妃でいたいわけでもないし、アンヌ・ド・ブルターニュを羨ましいとも思わないが、貴女が王妃だと何年もちやほやされた挙句、風見の鶏がちらりと別の方を向いただけでぽいと捨てられたなんて、とんでもなく滑稽だ。
祖国に帰るのが憂鬱で憂鬱でしょうがない。
一体どんな顔をして帰ればよいのか。
いっそのことパーッと盛大に派手に帰ろうか。
……いや、それでは悲しみのあまり壊れたと思われる……。
「それにしてもボージェさん、この町はどうしてこんなに暗いのですか?」
自分の鬱々しい心情を抜きにしても、春の歌声を空耳できるようになった季節の町とは思えないほど、彼も町も沈んでいた。
違和感はこのあたりの地域に入った時から感じていた。芽吹きの気配が運ぶあの心の浮つきが、意味のない喜びが、無駄なきらめきが、どこにもないのだ。
そうしてはいけないように、それは許されざることであるように、人々はうつむき、背を曲げ、必要最低限しかしゃべらず、足早に歩み去る。
路地には看板のひとつもなく、物乞いもおらず、露店商の姿もなく、花を飾る鉢のひとつもなく。
さえずり交わすメジロの群れや小さな花びらの川が上空を横切っても、彼らはずっとこうなのだろう。
ひたすら何かを背負って頭を垂れ地面を凝視し続ける。
「貴方も、この町全体も、とても暗いわ。やっと冬が終わるというのに誰も嬉しそうに見えません。もしかして、領主様が厳しいの?」
少女は青い目で屋敷の主人を見据えた。
フランスの頭脳と謳われるアンヌ・ド・ボージューに鍛えられただけあってか、淡い視線のわりに他人の芯を射る。
「話してご覧なさい。話さない方が良かったと後悔したなら、その時は聞かなかったことにするから」
「…………」
男が目を落とす。
黄昏の金色が部屋の中に長い影を作っていた。
「いえ、我々には姫君に心地よくご滞在いただくという使命がありま……」
「陰気すぎて、すでに心地よくはないわ」
隠されると意地になってしまう。
「それが使命なら話してくださいませんか?」
もう一度押し問答になったら止めよう──そう区切りをつけようとした時、
「今度は、私の娘が吸血鬼に差し出されることが決まったのです」
屋敷の主が目を伏せたままつぶやいた。
「吸血鬼?」
聞き返しながら、マルグリットの脳裏に浮かんでいたのは、その昔アンボワーズ城で出会った魔物の少年の姿だった。だぶだぶ法衣に身を包んだ彼は、あの頃唯一彼女と対等に接してくれる話し相手だったが、彼の主人は夜の世界を抱き昼の世界にまで爪をかける不滅の吸血鬼なのだ。
人々が畏れ、教会が追う、闇の代名詞。
「この町より山の奥へ行ったところに古い城がございます。避暑のために造られたような城で、かなり昔から誰も住んでいなかったそうです。けれどいつからか吸血鬼たちが棲み着くようになり……彼らの度重なる襲撃に疲弊した周辺の町々は、神への背約と知りつつも苦渋の思いで彼らと協定を結ぶことにしたのです」
「協定?」
「こちらは定期的にエサとなる生贄の人間を差し出す。向こうは協定に参加した町を襲ってはならず、彼らの組織下にない魔物は追い払う。それが交わした条件です」
──魔をもって魔を制す。
「一の犠牲で百を守る、ということですか」
大きく息をつくマルグリットの言葉に、仕方がないのです、とボージェ氏がうなだれる。
「教会にお願いして聖騎士様に来ていただいたこともあります。それでも吸血鬼を滅ぼすことはできず……教会も本腰を入れてはいなかったのでしょう、こんな山奥の貧しい町、そのうち陳情しても放っておかれるようになりました。ですから、我々には選択肢がなかったのです。領主様や町の代表がお決めになったこと、嫌だと言ってみたところでではどうすればいいのかと問われても答えようがありません。誰かが犠牲になれば、それ以外の皆の安息が得られる。……仕方のないことだったのです」
彼は自身に言い聞かせるように、しかし感慨を締め出すように、矢継ぎ早に続ける。
「しかもこんな協定、吸血鬼たちにとっては半ばどうでもいいものなのです。彼らは、エサが自動的に手に入るという少しの便利を手に入れただけで、いつ反故にしたってたいした痛手は受けません。しかし我々にとっては死活問題です。向こうが約束を破らないか常に息を詰まらせ、誰かが情にほだされて生贄の娘を逃がしてしまうのではないかと疑心暗鬼になっています」
魔物との約束など、薄氷の上を歩むようなものだ。
その終わらない柔らかな苦痛が背約の代償として神が与えたものならば、いつ訪れるとも知れない夜襲に眠れない夜を過ごすことが神への愛なのか、故郷を捨て新たな拠り所を探して流離うのが愛なのか。
「今月はこの町が生贄を出す番で──」
「選ばれたのがあなたの娘なのですね?」
「……そうです」
吐き出し目を伏せる屋敷の主に黄昏の影が圧しかかる。
屋敷ごと彼を押し潰さんばかりのそれはきっと、この町の人々の仄昏い期待だ。
娘が死ねば町が救われる。
口に出す者はいないが、無言の期待が町中にたゆたっている。途絶えることのない祈りの声にも似た、悪意のない期待。
どこかが犠牲を負えば、どこかが助かる。
そして犠牲を負うのはいつでも弱い方だ。
「…………」
マルグリットは肘掛に肘をのせ、形の良いあごに手をやった。
魔物の無差別な虐殺を封じるため、生贄を差し出すという例は実は少なくない。中には人間を狩ることそのものが好きな魔物もいるが、派手にやって聖騎士だの始末人だのと対峙するよりも、危険を冒さずエサを手に入れる方を選ぶ魔物も多いのだ。
しかしこんな偶然があるだろうか。
フランスを追われた元王妃がたまたま泊めてもらった屋敷の娘がちょうど吸血鬼の生贄にされるところだった、なんてことが。
しかもこの屋敷を宿泊先に用意したのはフランス側だ。
「ねぇ、私が身代わりになるのはどうかしら?」
口が滑ったというのか、マルグリットは大した考えもなく言っていた。
「私がお嬢様の代わりにその城へ行きます」
「そんな、いけません!」
ボージェ氏がそれこそ死人のように顔色を変えて、忙しなく腕を振り上げ振り下ろす。
「姫君に何かあれば、私はフランス国王陛下と皇帝陛下にどんな申し開きを──」
「あなたが謝る必要はありませんし、ないようにしておきます。私は町で噂を聞いて憤慨して吸血鬼の城に乗り込むのです。これなら問題はないでしょう?」
アンヌ・ド・ボージューに言わされている台詞だという気はしている。
あの有能な女摂政は、マルグリットが生贄にされる娘をそのままにしてフランドルへ帰れるはずがないと計算して、この町とこの家を帰路に組み込んだのだ、きっと。
マルグリットの正義と、情と、フランドルに帰り難い憂鬱を知っていて。
しかし、教会もフランスも自らの民が虐げられていると分かっていながら見て見ぬふりをする、それは為政者としてあってはならないことのはずだ。
何か斬り返してやりたい衝動が湧いてくる。
「私も易々殺されに行くつもりはありません。貴方は内密に腕の立つ聖騎士を用意してください」
「たかが聖騎士ではあの城の吸血鬼は斃せません。そんなことはもう何十年も前に試していますよ、先ほど申し上げたではありませんか」
「私は戦いに行くわけではありません。話をしに行くのです」
「吸血鬼とですか?」
言外に、何を今更、話など出来る相手か、という呆れが含まれている。
「貴方たちはその吸血鬼と話し合って協定を決めたのでしょう?」
「え……えぇ、まぁ」
十と数年生きただけの小娘に押し切られつつある中年の男。
「早く支度なさい。私はこれからその城へ行きます」
我侭を言えば世界が従うと思っていると思われているのが高貴な身分の特権だ。
「こ、これから!?」
敬語も忘れて男が目を剥く。
マルグリットは大きな青い目でにっこり笑った。
「善は急げと言います」
色々な大人が動く時間を与えると面倒なことになる。フランスがこれ以上画策できないように、教会の本体が是が非でも引き留めにくる前に。
「私と一緒に城へ行ってくださるような勇気ある聖騎士がこの町にいるかしら」
◆ ◇ ◆
「アスカロンとシャムシールが城へ向かっているそうです」
「あの城に得体の知れない化け物が居座ってるもんだから結果の報告が遅れている。まぁ、乗じて探りに行くにはちょうどいいか。シャムシールとマルグリット皇女にはつながりがあるんだろう? 皇女のいい護衛になる」
「えぇ、そうかもしれませんね」
「全く町の奴らは何考えてるんだか。皇帝の娘を吸血鬼の生贄にするとはね」
「アスカロンやシャムシールを伴えば、すぐユニヴェールの耳に届くことになりますね」
「ちょうどいいだろう、ミトラによれば他では優秀な結果が出ているらしいし」
「……そうですか、結果が出ている」
「“汝ら、神の如くならん”──畏るべき才能の持ち主だよ、ファウスト先生は」
ひとりが椅子に深く背を預け、憂いとも揶揄とも取れるため息をつく。
ひとまわり以上老けてはいるが、あの男と同じ系列の蒼眸で天井を仰ぎながら。
「この町の結果を知るまでもなく、実験は成功だ」
「…………」
「“実験”という言葉が気に入らなかったか?」
奇人の巣窟であるデュランダルにあって最もまともな大人だと称される男が、窓際に立つもうひとりに沈黙の意味を尋ねる。
「……いえ」
「誰も気付かなければその事象は起こっていないも同然だ。気付いていて気付かないふりをしているのなら、同罪だ」
「そうではなく──」
窓枠に手をかける優男は再度否定して、橄欖石の視線を滑らせる。
「標的に暗黒都市に依存していない吸血鬼たちを選んだのは確かですが、全滅しそうな時くらい報告するなり助けを求めるなりすればいいのにと思って」
「だが、監視の限りそれはなかった」
最もまともであることは往々にして最も苦労人であることと同義だが、この男は違う。
「それが奴等だろう。今までもそうだったし、これからもきっとそうだ。だからこそこの結果には意味がある」
この男は、まともな感覚を持ったまま流れに身を任せる術を心得ている。客観視点を持つ常識人のまま、あらゆる業務を忠実にこなすことができる。彼の辞書には、彼自身の状態を指す“矛盾”という言葉はない。
「……実験の主でいるつもりの我々は、果たして本当にそうなのでしょうかね」
優男のつぶやきに、常識人は目を細めてまたため息をつく。
「……アンタ、相変わらず面倒くさい性格だな」
「…………」
◆ ◇ ◆
──いた。
「本当に行かれるんですか? マルグリット皇女」
マルグリットの前に膝をついた聖騎士は、ヴェルトロ・レンツィと名乗った。
「そう決めました」
「……そうですか」
獅子の鬣のような赤毛は挑戦的で、しかし嘆息混じりに上げた顔はまるで近所の気さくな若い神父だ。託児所を兼ねてしまっている教会の神父。
誰からも一目置かれる聖騎士のはずなのに、押しの弱さと若干の頼りなさを漂わせている。
「吸血鬼との交渉でしたら私だけで参ります。そもそもこの地域の聖騎士隊が吸血鬼との取引を──国民の被害を容認していたことに問題があるんですから。お恥ずかしながら」
白銀の騎士服からのぞく内襟は、陽光を受けて輝く海の碧。髪の赤と相まって、ひとりだけ溢れる春をまとっている。
「だからこそ第三者が行くべきではありませんか? 貴方個人を疑うわけではありませんが、今まで放置してきた騎士隊の言葉は信用できません」
「……そうですよね」
なんて弱気な男なのだ。
面子第一主義の教会の人間のくせに、何ひとつ反論しないとは!
「そうおっしゃると思いましたので、私がお供致します」
説得など端から諦めていたのだろう。
「御身に傷ひとつ付けさせは致しませんので」
ヴェルトロは気負った様子もなくさらりと付け加えてくる。
虫を殺すことさえためらいそうな男が、随分と自信のあることだ。
「…………」
マルグリットはグラスに注がれたワイン色の離杯に口をつけ、微笑んで尋ねた。
「貴方、魔物は斬れますか」
「もちろんです」
男が少女を仰ぎ見たまま、腰に携えた剣を抜く。
鋭い切っ先にロウソクの光がさらりと斬られ、美しい剣身の上を流れていった。聖騎士という称号を持つ者の手にあるこそふさわしい、白く冷たく美しい刃。
しかしそれは、一介の聖騎士が手にできるような代物ではなかった。よくよく注視したなら、その身に彼自身の名が刻まれているのが見えたかもしれない。だが戦いとは無縁の花園で育ったマルグリットには剣の優劣の区別などつかないし、名が刻まれているから何だということも知らない。
「吸血鬼が眠っている昼間に行かれた方がよろしいのでは……」
部屋の入り口で遠慮がちにボージェが口を開いてきたが、
「生贄の娘の引き渡しは昼間に行われるのですか?」
「……いえ」
「でしたら、いつもと同じように致しましょう。私たちは寝首を掻きに行くわけではありませんもの。まずは交渉をするのです」
マルグリットは一蹴した。
「賢明なご判断です。始めから敵意を持って接しては無意味な戦いを誘発します」
剣を鞘に戻し、ヴェルトロが立ち上がる。
「もし妥協空しく戦いになったらこの聖騎士様が助けてくださるそうですし」
マルグリットも裾の短い濃紺のドレスをつまみ、椅子から降りた。
ここで吸血鬼に殺られれば確かにフランスの思うつぼだろう。
もはや身内ではなく神聖ローマ帝国皇帝の婚姻カードとなった皇女は、その政略結婚によってはフランスの脅威となりうる。今のうちに暗殺しておきたいが、あからさまでは諸国の疑惑の目が痛い。
皇女が妙な正義感を起こして吸血鬼に喰われてくれればもうけもの──程度の策にがっつり飛び込むなんて、アンヌ・ド・ボージューの高笑いが聞こえてくるようだ。
分かっている。
この町をこのままにして置けないという正義感が半分くらい、離婚された王妃という名札でフランドルへ帰るのが嫌だというのが半分くらい。
それを天秤にかけた結果がこれだ。
このままフランドルへ帰り憐れみと失望が混じった視線を受けるくらいなら、若さゆえの浅慮で愚かな正義感を振りかざした皇女と笑われた方がまだ少しだけマシ。
何故ならそこには、自分の意志が入っているから。例えそれで命を落とすことになったとしても。
「お任せください。私の命に代えてもお守りします」
彼女の退室を待つ聖騎士が恭しく胸に手を当てる。袖口からちらりとのぞいた白い手袋の端には、羽を広げた鷲の紋章。
「実は私がここカプラに派遣されたのはごく最近のことで、以前はマルセイユの聖騎士隊で隊長を務めていました」
プロヴァンスの太陽と地中海の恩恵にたっぷりと浸る港町、マルセイユ。
男の襟からのぞく碧色は、その海原のきらきらとした波間を切り取ったものだろうか。
「ちゃんと実績はありますから、ご安心を」
にっこりと、やはり頼りなげな笑顔を向けてくるヴェルトロ。
しかし、なぜイタリアの名前を持つ男がマルセイユで聖騎士に叙され、そしてマルセイユのような大きな都市からこんな北部の辺境へ飛ばされてきたのかの方が気になる。
心配になって吸血鬼と剣を交えることになった場合の策はあるのかと問えば、無策で隊長職は務まらないという答えにならない答えが返ってきた。
「貴方の腕を信じましょう」
「損はさせません」
「…………」
普通はこれだけ断言されたら心強く思うものだが、そういう気持ちが欠片も湧かないのは、もはやこの男の才能と賞賛するしかない。
城へ向かう夜の森は、さながらダンテが目覚めた暗闇の森のように鬱蒼とした恐怖に満ちていた。人の命も魂も寒風に音を立てる一枚の枯葉と同じ、色のない荒涼とした絵はひたすらに死に似て、彷徨える者の息吹を凍えさせる。
青く灰色の霧が漂う木々の間、棘を剥き出しにした茨、立ちはだかる静謐な野生のうねり、物言わぬ林冠、すがるには細すぎる月、道なき道を強引に車輪を転がす二輪馬車。
フランスの南に入り口があるという暗黒都市がこの闇の向こうに茫漠と広がっているのではないかと錯覚する、境界の森。
そんな現実と幻想が入り混じる曖昧な世界を延々と進んでいると、突然何かの気配に怯え馬が立ち止まった。
「どうしましたの?」
あまりの悪路にくらくらする頭を抑えて御者台に訊くと、
「馬車が、もう一台」
抑えたヴェルトロの声が返ってきた。
「あら、ほんと」
身を乗り出して見ると、立派な四輪馬車が彼らの行く手を遮っている。
「これ以上この馬車で行けるわけないじゃん。なにこの獣道。なんでこんなデッカイ馬車で来たのさ!」
「お前、パーテルから安馬車で来たかったのかよ! 骨がバラバラになってアゴ外れるぜ」
「下の町で乗り換えてくれば良かったねぇ」
「んもう、アスカロンはいっつも使えない!」
「道もねぇような山奥にある城だなんて聞いてなかったんだよ!」
「地図見たときに気付かないの!?」
「お前は奴がどれだけ適当な地図を描くのか知らねぇのかよ! お前の報告してくる地図並みなんだからな!」
何やら三人の乗員がその馬車から降りてにぎやかに喚いている。
ひとりはすらりとした異国の風貌、ひとりは素行のよろしくなさそうな若い男、そしてもうひとりは──。
「シャムシール!」
マルグリットは思わず声を上げた。自らの馬車の御者台に聖騎士がいることを忘れて。
「あなた、シャムシールね?」
アンボワーズの光溢れる庭でふたりで動物たちと遊んでいたのはいつの頃だろう。フランス王妃の玉座を取り上げられた時には、少年に八つ当たりをしてしまった。しかもそれ以来彼は彼女の前から消えてしまったのだ。
彼女は流れた月日の分だけ成長したが、不良青年へ叫びかけた文句を飲み込んで振り返ってきた少年はあの頃とまるで何も変わらない。
大きな目と可愛らしい栗毛、だぶだぶの法衣。
彼はしばしぽかんとしていたが、鼻をひくつかせたと思うと「あぁ!」と手を打った。
「マルゴ!」
そして満面の笑みをこちらに向け、すたすた歩いてくる。
「やっとフランスから離してもらえたんだねぇ。皇帝陛下のところへ帰るところ?」
マルグリットは馬車から飛び降りた。
「サンリスの和約が結ばれたのは、あなたが力を貸してくれたからだって聞いたわ、ありがとう。あのままだったら私、一生フランスから出られなかったかもしれない。最後に会った時には私、ひどいことを言ってしまったのに」
「それはもーいーの」
さっきまでフランドルへの帰還で暗澹としていたのに、口からはすらすらと感謝の言葉が出てくるのには自分で笑ってしまう。
しかしどちらも本物の気持ちなのだから仕方ない。それは矛盾ではなく、別の線上に存在している感情というだけなのだ。
「アンヌ・ド・ボージューがあなたの名前を出して苦虫を噛み潰していたのよ。あの顔見せたかった!」
「僕も見たかった! あのおばさんいつもお高くとまってるんだもん!」
少女と少年はきゃいきゃいと馬車と馬車の間で手を取り合う。
御者台の聖騎士は動かなかったが、その目は、もう一台の馬車の傍に佇む二人へ。そしてその二人も隙のない目を聖騎士に向けている。
「でもどうしてシャムシールがここにいるの? あなたのおうちはもっと南の方でしょう?」
マルグリットのその言葉に聖騎士の眉が少しだけ反応する。
「今はお使いの途中〜。この先の城に住んでる吸血鬼に手紙を届けに行くんだよ」
「偶然ね! 私もその城に行くところ」
「へぇ、なんで?」
「私、その吸血鬼への生贄なの」
「はぁ!?」
シャムシールが素っ頓狂な声を上げ、ぐっと口を曲げる。
馬車の近くにいる大人二人も顔を見合わせている。
「なんで神聖ローマ帝国の皇女がそんなことしてるの!」
「なんでって……町の人が可哀想だったんだもの。話し合いでなんとかしようと思って……」
「帰るのがヤなんでしょ」
子どもは時々グサリと図星を突く。
「みんなに“あれが離婚された皇女ねー”って影で言われるのがヤなんでしょ」
しかもこの少年は彼女よりはるかに長い年月を生きていて、そんなくだらない人間の機微など腐るほど見てきているはずだ。
隠しても取り繕っても無駄。
「──そのとおりです」
正直にうなずき事情を説明すると、少年が目を吊り上げた。そしてずいっと一歩前に出てくる。
「バカバカバカ! いい? マルゴの救出にはうちのメイドが関わっててね、それがまた目端が利く守銭奴でね、自分の働きで救った皇女が自分から命を投げ出して吸血鬼に喰われたなんてことが知れたら、自分は無駄骨を折った! なんて文句言って、その働き分をお父上である皇帝陛下にたっぷり請求するような奴なんだよ!」
少年の背後で、不良青年の方が引きつった笑みを浮かべている。
「そんなことになったらどうするの!? こう言っちゃなんだけど、マルゴのお父上はいつだってお金に困ってるでしょ!? うちのメイドが請求する額が払えるわけないよ! そしたらお父上は自動的にユニヴェール様を敵にまわすことになるんだからね!」
「う……それは困るわ……」
「町の人を助けたいのは分かるけど、喰われてもいいかなんて半端な心構えで行って、本当に喰われたらそういうことになるの。分かってる!?」
誰もがその名を知っているパーテルの吸血鬼がただの世界の敵ならば話は簡単だが、あの化け物は単純に人間をエサと見ているわけではなく、その歴史と構図の中に滑り込み各国各人に糸をつけている。
動かすための手綱ではなく、動けばそうと知れる蜘蛛の糸を。
そうして度々歴史に介入する。より楽しく、より劇的な流れを演出するために。
だから、ヴァチカンはともかく各国の要人たちは、彼を「滅ぼすべき者」とみなす一方で「味方につけるべき者」としても認識している。
フランスが未だに主君面をしてシャルル八世の戴冠式に彼を呼んだのが良い例だし、マルグリットの父マクシミリアンも道化師クンツの計らいで会見したことがあるのだ。
「…………」
「皇女は喰われませんよ。私が付いていますから」
マルグリットがシャムシールに返す言葉を探していると、御者台から穏やかなヴェルトロの声が降ってきた。
「誰、アンタ」
そこで初めて少年が顔を上げ、聖騎士の姿を瞳に映す。
「ヴェルトロ・レンツィ。彼女の護衛です」
「こんな寂れた町に吸血鬼始末人がいるのっておかしくない?」
シャムシールが双眸を険しくした。
しかしそれ以前に──彼は聖騎士ではなく吸血鬼始末人なのか? マルグリットは問いを込めて振り返ったが、
「聖騎士が束になっても敵わなかった吸血鬼が相手ですから、今更聖騎士を護衛につけても意味はないんです」
説明はなく、しかし台詞から肯定だと判じることができる。
「それがおかしいって言ってるの。僕らだってね、行く先のことくらい調べるんだからね。下の町と城の吸血鬼の関係だって知ってる。アンタたちが今まで放っておいたのは、単にここが辺境の町なのと、町々に契約させておいた方が被害が少ないからでしょ。なのに何で皇女の訪問にあわせて吸血鬼始末人が配属されたのさ」
「皇女がご滞在されるからです。彼女が吸血鬼の城へ行きたいと言い出さなくても、私は彼女の護衛をする予定だったんですよ」
「だから! 契約してるってことは、言いかえれば生贄さえ渡していれば他の町より安全ってことでしょ。それなのになんで吸血鬼始末人なのさ」
「念には念です。皇女にもしものことがあったら困るでしょう? 要人をお預かりするということは、始末人を雇うほどの万全な対策を要求されることなのです」
「念には念を入れておけば、もし皇女が吸血鬼に殺されちゃっても言い訳が出来るもんねぇ!? 護衛には吸血鬼始末人まで配置しましたがって」
つまりシャムシールはヴェルトロがフランスの手先なのではないかと言いたいのだ。
彼がフランスから頼まれたのは彼女を城まで連れて行くことであって吸血鬼から彼女を護ることではなく、その結果彼女が喰われたとしても、フランスは「吸血鬼始末人を雇って護衛した。これ以上何ができただろうか!」と皇帝マクシミリアンに申し開きができるというわけ。
始末人の中にもヴァチカンの手下ではない“フリー”というのはいる。上司が選べるのが利点だ。
だが──
「どうでしょう。この町も私も責任は追及されると思いますよ、どんな対策をしていたとしても、皇女の身に危険があれば」
まっとうな意見を子どもを諭す口調で言われたのが気に入らなかったようで、シャムシールが足を鳴らして口を尖らせた。
「誰もアンタの心配なんかしてないよ! マルゴに何かあったって、結局フランスはアンタと町に責任を押し付けて終わりでしょ!」
「うーん、確かに」
それでいいのか始末人。
「こんな奴に護衛してもらうことなんかないよ、マルゴ。城に用があるなら僕たちと行こうよ」
「え?」
シャムシールに腕を掴まれたマルグリット。
「城の吸血鬼がグダグダ言ったら滅ぼしちゃえばいいんだよ。今日はアスカロンが一緒だから、そんなこと簡単だよ」
さっき、その吸血鬼へ手紙を届けに行くとか言っていなかっただろうか。
案の定その“アスカロン”と思しき青年は、馬車に寄りかかり平坦な目で少年を睨んでいる。
「ユニヴェールの三使徒なんかと行かせたとなると私の首が飛びます」
「なんかって何!?」
「いえ……聞き間違いでは?」
ギンっと眼光を鋭くするシャムシールと、ふいっと顔を背けるヴェルトロ。
「えーと……」
人生経験が短いマルグリットには、この状況を素敵におさめることのできる名案は浮かばなかった。
「とりあえず、」
だから両手を合わせて努めて明るく言った。
「みんなで参りましょうよ」
◆ ◇ ◆
馬車は途絶えた道に残し、ヴェルトロがマルグリットを乗せた葦毛の馬を引き、アスカロンがシャムシールと店長を乗せた青毛の馬を引いて小一時間、突如として森が開けた先に見えたのは湖だった。
波のない水面には靄がかかり、対岸は見えない。
ヴェルトロがランタンに布をかけ、闇に眼を慣らし月光のみで様子を伺うが、深い山の中の湖だという以外何も分からなかったようで、軽く首を左右に振った。
しばし息を殺していると、水鳥の羽音が水文の如く広がる。
「あれだよね」
シャムシールが指差す先には、湖の岸に沿って建てられた石積の城が姿を現していた。さっきまでは霧で隠れていたのだ。
「あれだな」
アスカロン──だと紹介された青年が手元の地図と見比べている。
「このあたりには他に城はなさそうだからな」
「意外と大きそうだね」
狩猟用か避暑用の城なのだろう。見たところ弓を射たり砲弾を打つための銃眼は見えず、風化した石の白と青い屋根の見た目はアンボワーズ城と重ならないでもない。しかしやはり平地の柔らかい印象の城とは趣が違い、こちらはもっと無骨で山岳の城然としていた。
つまり、舞踏会やお茶会を開く雰囲気ではない。
「……城門が開いていますね」
ヴェルトロが近くの木に馬を繋ぎ、マルグリットは地面に降ろされた。
「伝書鳩を飛ばしましたから、開けておいてくださったのでしょう」
夕方飛ばした鳥が暗くなる前にここに辿り着いたのかどうかはともかく、湖へ流れ込む川の上に架けられた跳ね橋は下がっていて、城は無言のまま客人を手招いていた。
それをアスカロンが眉を上げて皮肉に笑う。
「橋だけ下ろして出迎えはナシか? 随分無愛想だな。吸血鬼ってのは無駄に形式美を追及したがるんじゃなかったのか?」
「人見知りなのかもね」
「いや、そうではないようだよ」
シャムシールのいい加減な推測を制したのはパリで商いをしているというメム店長だった。店の名はなんといったか……そう“ナルバートン商会”。それなりに大きな商業組織の支店なのだというが、人生の多くをアンボワーズの花園の中で過ごしたマルグリットは聞いたことがなかった。
「ホラ」
ずかずか城門を過ぎた店長が城の入り口を指差し、
『!』
後に続き目を凝らした男たちが一瞬息を止め、ヴェルトロがマルグリットの行く手を遮る。
「……ヴェルトロ、邪魔です」
「皇女は見ない方がよろしいかと」
「死体だから」
真実を言わないと駄々をこねると分かっているのだろう、ミもフタもなく付け加えてきたのはシャムシールだ。
「吸血鬼のだね」
「シャムシール、あなた分かるの?」
「匂いでね」
「ふーん」
「皇女!」
制するヴェルトロの後ろから覗いてみれば、想像したのよりずっとかさついた眺めがあった。
建物内部はなんだかごちゃごちゃしている様子だが、夜のヴェールがかけられていてはっきりとは分からない。しかし丸天井の中心から吊り下げられた大きなシャンデリアはよく見えた。火のないロウソクが何十本も冬の枯れ木のように乱立していて、火を灯せばさぞかし豪奢にこの湖畔の離城を照らすことだろう。
しかし今やその中心からはそぐわぬ縄が伸びていて、その先にまるで振り子のように人間らしき者が宙ぶらりんになっている。
黒尽くめの、なんとなく干乾びた、死骸。
あけすけな光がないのと臭いが何もないのと血の一滴も流れていないことが、それを凄惨というより間の抜けた光景にしてしまっている。
「吸血鬼の死体……ってあるんでしたっけ?」
ヴェルトロが見上げたままぽかんとつぶやいた。
「普通はないねぇ。彼らは斃されるまで滅びないし、斃されれば灰になっちゃうから」
色のない乾いた空間の中、メム店長の声だけが鮮やかな湿り気を帯びている。
「吸血鬼の死体ってのは本当に珍しい。何故彼は再び死んだんだろうねぇ」
だがその謎々を解く時間は与えられず、ホールを歩き回っていたアスカロンが大きな鏡の前で立ち止まった。
「この鏡の先に地下牢があるな。女の声がする」
「今まで生贄として連れて来られた娘さんたちがまだ生きているんでしょうか?」
かがんで床を調べるユニヴェールの使徒にヴェルトロが近付いた。
「開けてみてください」
「なんでお前に指図されなきゃなんねェんだよ」
「一番近くにいるんですもん」
「俺もシャムシールも、吸血鬼のエサなんかに興味ねェ」
「……じゃあ私が開けるので退いてください」
隠し扉ひとつ開けるだけで、なんだか無駄なやりとりだ。
そして、
「シャムシール、ここで待っとけ。店長、ふたりを頼んだぜ」
「はいよ」
いつの間にか、地下にはふたりで降りて行くことになったようだ。
アスカロン曰く、ヴェルトロとシャムシールを一緒にしておくのは危険。ヴェルトロ曰く、マルグリットとアスカロンを一緒にしておくのは危険。いわゆる利害の一致というやつだ。
鏡の扉を開けた先には壁面にロウソクが灯された螺旋階段が続いており、両人は互いに何やら文句を言いながらその声は少しずつくぐもってゆく。
マルグリットは彼女の横を動かない少年の肩をつついた。
「シャムシール、大丈夫? ヴェルトロはクルースニクなんでしょ? ふたりになったところでアスカロンを討つつもりなのではないかしら」
「大丈夫。やられそうになったって、アスカロンは闇に逃げ込めるから」
そもそもただのクルースニクに追い詰められるほどアスカロンは弱くないけどね、そう付け足してくる口調は自慢げでもなんでもなく、彼にとっては当たり前のことのようだった。
「マルゴ、寒くない?」
「大丈夫」
大丈夫の応酬をしていると、城内を観察していた店長が喉の奥でくつくつと笑ってくる。
「マルグリット皇女はシャムシールが怖くないんだねぇ。ユニヴェールの三使徒って言ったら、暗黒都市の住人もあまり寄りたがらないのに」
「今更怖がれって言われたって無理だわ。小さい頃、ずっと遊んでたんですもの」
今では見た目が逆転してしまったけれど。
「そう」
彼の切れ長の目がさらに細まる。
「──だけど、魔物を怖れないのも困りものだよ。生贄の身代わりだなんて、勇気だけでどうなるものでもない。相手が食屍鬼じゃなく吸血鬼なら話ができると思うのも大間違いだ。シャムシールみたいに悠長な魔物の方が珍しいんだからね」
「悠長って」
少年が頬を膨らます。
「でも本当のことだろう? 君たちの後ろにはユニヴェールがいる。君たちは例え何がどうなろうと、最後には彼が出てきて君たちを助けてくれると信じてるはずだ。ジェノサイドの時だって、君たち誰ひとり彼が滅んだなんて一片も思わなかったろう?」
「うん」
「だが普通の魔物はそんな後ろ盾はないんだよ。誰かが助けてくれるなんてありえない。それにねぇ、特に吸血鬼は一度死を味わっているから、彼らにとって滅びは恐怖だ。彼らは何が何でも生き延びようとするし、滅びを回避しようとする。──必死なんだよ」
言葉にあわせて男の手や腕が弧を描いて踊る。
「恐怖は理屈じゃないからねぇ」
アラビアの魔術師のような真顔で、葡萄酒のような声音で。
「それは本能で攻撃にすり替わる」
パリの仕立て屋は何故こんな話をしているのか。
真意を測りかねながらマルグリットは思いつきで反論した。
「でも魔物には暗黒都市があるでしょう?」
「暗黒都市は在るだけだよ。世界の裏側に、魔物を抱き込んで広がっているだけだ」
それに、と続けた店長がしゃがんでにっこり笑ってくる。
「君たちの国だって利害でしか動かないでしょ?」
「…………」
助けてと村人ひとりに頼まれて動く国はない。
それは確かだ。
マルグリットが言葉に詰まって黙っていると、
「テンチョー、そういえばここに来る途中言ってたよね。この城にはテンチョーが興味を持つものがあるって」
シャムシールが空白を埋めてくれた。
「言ったよ」
「それって、コレ?」
少年が未だに吊るされている吸血鬼の死骸を仰ぐ。
魔界の店長は答えを言葉にはせず、マルグリットに向けたものと同じ笑顔を少年に向ける。
「知ってたの?」
「知ってたというか、だから呼ばれたというか」
彼はわざと曖昧にして少年の棘を楽しんでいる。
「誰に呼ばれたのさ」
店長がその問いを無視して腰を上げたと同時、
「──シャムシール、生きてるか?」
水と油が帰ってきた。
……誰も助けずに。
Menu Next
Home
BGM by Two Steps From Hell [Everlasting] Thomas Bergersen [Merchant Prince] Nightwish [Storytime]
Copyright(C)2012
Fuji-Kaori all rights reserved.
|