第23話 スリープレスナイト
後編
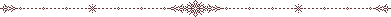
「手ぶらかい?」
メム店長が首を傾げると、アスカロンがケッと吐き捨てた。
「このクルースニク様は、人間を助けるよりも魔物を退治しに行く方を優先させたいんだとよ」
「その言い方には語弊がありますよ」
ヴェルトロが珍しくムッとした顔をみせる。
「でも結局そういうことだろ。アンタたちはあの女どもを連れてさっさと町に帰りゃいいのによ」
「今この城には誰が──あるいは何が──いるのか、本当に吸血鬼は全滅したのか、それらが分からないのに戻れませんよ。それとも私が彼女たちとじっと地下で待っていれば、貴方が城の中を調査してきてくださるんですか?」
「ヤなこった」
「では貴方が彼女たちを見張っていてくれますか?」
「そんな義理はねェな」
「ほらぁ」
「何が“ほらぁ”なんだよ、お前が言ってることは普通全部“部下”にやらせることだぞ」
「“部下”じゃなくて“仲間”に置き換えてみてくださいよ」
「俺とお前は仲間か?」
「違います。あ、そうか」
「……あぁもう何なんだよコイツ」
アスカロンが手で顔を覆って天を仰いだ。
大幅に失望されているヴェルトロはそれにはお構いなしで、こちらに向かって真面目な顔を向けてきた。
「さしあたって彼女たちが危険にさらされる可能性は低いと思われます。調査をする間連れ回すより、あの地下牢にいてもらった方が安全でしょう」
この大人たちは地下から上がってくる道中、ずっとこんな調子だったのだろうか。
それにしても、
「──この城に誰がいるかって、吸血鬼ではなくて?」
マルグリットが腰に手を当てると、白のクルースニクがすっと眉を寄せた。
「順を追ってお話しましょう」
彼の赤い髪は暗闇にあって黒と同化することを拒絶し、未だその彩度を保っている。それだけがこの場にある暖かな色だ。
「地下には、近隣の町から生贄に送られたご令嬢が数人囚われていました。彼女たちの話を総合すると、二ケ月程度、吸血鬼の犠牲になっている方はいないようです。彼女たちに食事を運んでいたのはこの城に棲む吸血鬼たち自身だったようですが、最近その者たちは現れず、代わりに新顔の大男が運んでくるそうです」
「新顔の大男?」
「えぇ。しかし今までその男が彼女たちを襲うことはなかったそうで、根拠はありませんが吸血鬼ではないと思う、とのことです」
「それでこの城の吸血鬼は全滅したかもしれない、別の魔物が居座っているようだ、という結論になるわけですね」
「えぇ。その魔物が吸血鬼を排除した可能性が高いですね」
城を制圧した証に死骸を吊るしたのだろうか──マルグリットがちらりとそれを見上げると、視界の隅でシャムシールがアスカロンを小突いているのが見えた。
「どうする? 吸血鬼が全部死んじゃってたら、ユニヴェール様からの手紙が渡せないけど。燃やしちゃう?」
「燃やすって、なんでそういう結論になるんだお前は。いいんだよ、問題ない」
鳶色の髪をした青年が虚空に視線をやったまま答えていた。口の端が笑っている、思案がどこかに帰結した顔つき。
「思い出して見ろ、確かに城には吸血鬼が棲んでいると聞いたが、吸血鬼に手紙を渡せとは言われていない。俺たちは“城主”に渡せと言われたんだ」
「じゃあこんな田舎の城を乗っ取ったその変な魔物に渡せばいいね」
「お前、無邪気にケンカ売るタイプだよな」
「でもどこにいるのかな。っていうか、普通その大男はただの使い走りだよね? 吸血鬼の群れを全滅させて城を乗っ取るような魔物が自分で娘さんたちに食事を運ぶわけないもんねぇ」
アスカロンの刺々しい嘆息を無視して、シャムシールが大げさに両手を広げた。
あごに手を当て素直にうなずくヴェルトロ。
「そうですね。まずはその大男か、親玉を探すことにしましょうか。生き残りの吸血鬼がいるかどうかも確かめながら」
「その必要はない」
夜更けの暗がりに響いた低い声は唐突だった。
予期せぬ闖入。
にも関わらずその声は、身構える必要があるか迷うほど投げやりでヤル気がなかった。
「こっちから来たから」
同時にシャンデリアのロウソクに火が灯る。
山城にしては悪趣味に飾り立てられた内部が露わになり、広いそこにぽつぽつと佇む者たちの影が四方八方に伸びた。
いきなりの明るさに目を慣らして見回せば、アラベスク調に彫刻がされた柱、次の間への入り口を固めるランスやハルバードを構えた甲冑、マルグリットの身丈ほどもある置物の猫は耳輪をしていて、素焼きなのかただの土くれなのか分からぬ背の高い壺が厳かに飾られ、壁には牡鹿の剥製、抜身のロングソードが何十本、身元不明のおっさんの巨大な肖像画……。
「女たちの言う大男は俺で、この城には今、お前たちと俺しかいない」
雑多な宝物に出迎えられて建物の奥から姿を現したのは、確かに娘たちの証言どおり大柄の、ボサボサの髪に眠たげな目つきをした男だった。
武人らしく筋骨逞しいが、それより何より目をひくのは、彼が羽織っている黒の外套の裏地だ。ヴェルトロの髪に劣らず彩度も明度も全開、異国の鳥や花や文様が所狭しと刺繍されている。
「──オッサン……」
知り合いらしいアスカロンが敬意に欠けるつぶやきを漏らし、絶句した。
「よお」
「……起きてるとはフランベルジェから聞いたけど、アンタがなんでこんな辺境の城にいるんだよ」
青年は何故かすごく嫌そうな顔をしている。
その反応が気に入ったらしく、男はニタリと笑って一言。
「暇つぶし」
ずっこけるアスカロンの横で、シャムシールが手を叩いた。
「じゃあさ、フェンリルが毎日娘さんたちのご飯作ったの? うっそぉ」
「おうよ。俺は見かけによらず何でもできるんだぜ──って、そんな真似できるかよ。あっちこっちの町で出来合い買ったんだよ」
「へぇ。それも可愛いね」
今度は男がこける。
だがその和気藹々とした輪の中で、ひとり凍りついている男がいた。
「……どうしましたの、ヴェルトロ」
マルグリットが名前を呼ぶと、別の声が──アスカロンが──反応した。
「あぁ、ヴェルトロ」
気さくな魔物の口元は笑っているが、目は笑っていない。
「アンタはクルースニクだから面と向かっただけで強さはある程度分かるだろ。見てのとおり、俺やシャムシールじゃこのオッサンには全く歯が立たない。つまりアンタもまるで相手にならない。だから妙な気起こすなよ。オッサンがキレたら、アンタひとり俺が助けてやれるかどうかも分かんねェからな」
「まぁ無理だろうな」
「うっせぇよ!」
寸劇を演じている鳶色の青年には目もくれず、
「…………」
ヴェルトロの碧眼は、着崩れた威圧感をまとう大男に向けられている。
しかし彼は呆然自失していたわけではないらしかった。
「……フェンリル、とは?」
落ち着いた、意志のある言葉が発せられる。
対して大男は靴音を反響させると、地下への入り口がある大きな鏡の縁取りに背を預け、手にしていた酒瓶を呷る。
「彼の名はヴァナルガンド・フェンリル。分かりやすく言うと北欧の狼」
いつの間にか進み出てきたパリの店長が、代わりに答えた。
彼は猫の如く足音を立てることなく大男の傍に寄る。並ぶと、頭一つ分高低差があった。
「皇女様もヴェルトロも北欧神話は知っているね? あぁ、それならいい。彼はそこに出てくる“フェンリル”だ。ずっと暗黒都市の地下に押し込められていたけど、最近また起こされた。でも力の大半は女王陛下に封じられているから、明日明後日に世界が滅びることはないよ、大丈夫」
金色の双眸が声の調子に合わせて大きさを変える。
「テンチョー、フェンリルと知り合い?」
「仕事仲間」
言って両方の口角をくいっと上げる。
「僕の仕事は糸を紡ぐことでね。例えば、アレから」
しなやかな手がぴっと天井を指す。
「吸血鬼の死体?」
「そう。珍しいでしょ? 僕がアレを紡ぐ、それを他の職人に織ってもらって仕立ててもらって、僕が売る。君たちのご主人に卸してる布だって珍品ばかりだろ」
彼はフェンリルの横を離れ、壁に沿って歩き出す。
「面白いものがあるからって、ヴァルから呼ばれてねぇ。ひとりで行っても良かったんだけど、世の中物騒だし」
ヴァナルガンド・フェンリル。略してヴァル。また思い切って縮めたものだ。
「普段は彼が僕の護衛をしてくれるんだよ。だから仕事仲間。最近は暗黒都市に繋がれて彼に頼めなくて大変だったんだから。客は珍しいもの欲しがるし、でもそういうのは大抵危ない橋を渡らなきゃならないし。とはいえ売り上げが落ちると上からガタガタ言われるし、あぁヤダヤダ」
「ちょっと待て」
物柔らかな振り付きで肩をすくめて見せるメリル・ジズ・メムに、アスカロンが平坦な視線を送っている。
「オッサンが暗黒都市の地下牢に繋がれる前から一緒に仕事をしてたのかよ。まぁ人間だとは思ってなかったが、店長、アンタ何者でいくつだよ」
男は猫の置物に手を置いて、こちらに向き直った。
「古いよ、僕は。もちろん君たちよりも、君たちのご主人よりも、白狼やベリオール、そしてヴァルよりも」
「アイエイエー島の魔女キルケよりも」
付け加えたのはフェンリルで、シャムシールとアスカロンとヴェルトロが一斉にギョッとした顔を作る。
「さすがに女王陛下の治世には全く及ばないけれど。ヴァネツィアで商売してたこともあるし、あぁ、そうそう、ちょっと前はよくフェニキア人たちの船に乗せてもらってねぇ。彼らは優秀な商人だったんだよ」
真っ直ぐ前を見据えすらりと座る猫と、その頭に手を乗せ寄りかかる男。マルグリットはその男の影に尻尾でも生えていないかと凝視してみたが、残念、見当たらない。
見つめられているのを知ってか知らずか、彼は繁栄は続かないものだよと大きなため息をついていた。
そこにもうひとつため息が重なる。狼の、ため息。
「メリー、お前の身の上話はもういい。全員引いてるだろうが」
「……そう? 聞いといて損はないと思うけど。僕の本質は誰も知らないからねぇ。──君も含めて」
唇の前に一本指を立て、店長が薄く笑う。目が据わっていたのは一瞬、すぐに人当たりの良い顔になり、手の平をフェンリルに差し出した。会話の主導権を譲ったつもりだろう。
「アスカロン、ユニヴェールからの手紙は」
「あるけど」
「……お渡しいただけるだろうか」
咳払いをしたフェンリルに近付いて行ったのはシャムシール。彼は美しい紙に包まれた手紙を狼に渡すと、手の平を上にしてそのまま突きつけ続けていた。
「……何だよ」
「ユニヴェール様がね、お駄賃は受け取った人からもらいなさいって」
「あの野郎、どういう教育してやがる」
「男が些細なことで文句言うのはカッコ悪いとも言ってやれ、って言ってた」
「分かった。後で家に届けてやる。ガリヤの菓子を、部屋が埋まるほど!」
「わーい」
そこで初めてマルグリットは大男が魔物でありながら紅の目を持っていないことに気付いた。黒にも見えるが、藍色にも見える。
「さて。手紙の内容はこうだ。“吸血鬼の死体を寄越せ。 ──シャルロ・ド・ユニヴェール”……相変わらず綺麗な字で味も素っ気もない手紙書くねぇ。時候の挨拶くらい書けねぇのかよ」
ぶつくさ言ってから、フェンリルが手紙を顔の横に掲げた。
「吸血鬼の死体は大人気だな、メリーも欲しいという。ユニヴェールもほしい。ここは友人歴の長いメリーに譲ろうと思うが、どうかな? ヴェルトロ・レンツィ」
「……はい?」
唐突に名指しされてヴェルトロが目を丸くする。
「君たちもコレが欲しいんだろう?」
「…………」
「君は皇女の付き添いでここに来たかもしれない。だが、この城に吸血鬼の死体が存在しているかどうかを確認する役目も負っているはずだ」
そこでマルグリットは手を挙げた。
「貴方は、吸血鬼たちが何故滅びたのかご存じなのですか? 灰にならず、身体を残したまま滅びた理由を」
「…………」
こちらを視界に入れてくる狼の両眼はほぼ死んでいるので怖くない。しかし何かを測られているような居心地の悪さが背筋を伝う。
「こいつらの死因は──」
狼が緩慢な動作で瓶の底を吊るされている吸血鬼に向ける。
「餓死だ」
「……餓死、ですか」
物乞いの多い街や痩せた村では珍しい話ではない。だが、近隣と契約して生贄を差し出させている吸血鬼が、しかも地下牢には食糧である娘たちがまだ生きていて、餓死。
意味が分からない。
炎に炙られた蝋が垂れる音まで聞こえそうな沈黙の後、草色の少年と鳶色の青年がほぼ同時に口を開いた。
「……パッセ」
「……ヨハン・ファウスト」
そして青年の方が白のクルースニクへと視線を滑らせる。
「俺の調べでは、錬金術師のヨハン・ファウストは現在デュランダルの副隊長だ。父親はゲオルク・ファウスト。知ってるか?」
「──いえ」
ヴェルトロの目が一瞬浮つく。
だがそれには触れず、
「アスカロン、お前心当たりがあるのか?」
フェンリルが青年を促した。
「あぁ。前に暗黒都市のオンズのひとりが血を受け付けない吸血鬼を飼っていて、そいつはそれをネタにヴァチカンと取引しようとしていた。ユニヴェール様が察知してエーデルシュタインを滅ぼしたから取引は未遂で終わったと思ってたんだが……その血がすでにヴァチカンに渡っていた可能性はあるな。おまけに向こうはパルティータの血まで持ってるときたもんだ」
「ファウスト二世が何か薬を作ったかもねー」
血は、吸血鬼が仮初の命を永らえる源。吸血鬼の存在の根源。
それが取り込めなくなる薬なんて、本当に作れるというのか。
「吸血鬼を変える薬か、人間を変える薬か、どっちかねぇ」
寄りかかったまま猫の額を撫でながら、店長が言う。
「あの底意地の悪いデュランダルのことだ、どっちも作ってるさ」
アスカロンが無意識だろう、シャムシールの頭に手をやる。
「オッサン、この城の吸血鬼はどっちか分かるか。ここの吸血鬼に何かの感染が広がったのか、人間の血が変わって吸血鬼が飲めなくなったのか」
「後者だ。俺はずっと経過を見ていたからな。変質した血を飲むと、普通の血も飲めなくなる。血液全般を受け付けなくなるわけだ」
「……彼らが飢えて滅んでいくのをずっと見ていたのですか?」
「俺は慈善事業をしに来たんじゃなく、暇潰しに来てただけだからな」
酒を呷りながらの回答は明快で、マルグリットの問いは一笑に伏される。
「フランスの吸血鬼が生き延びようが滅びようがどうでもいいさ。それに城に棲みつくような吸血鬼は矜持の高い生き物だから、何があったって狼なんかに助けは求めんよ」
「暗黒都市にも?」
「お嬢さんの国では──」
フェンリルが鏡から身を起こし、酒瓶を手放す。耳障りな音を立ててガラスと液体が飛び散り、床に飛沫の傷跡が付く。
「王の居城に陳情に来た村人のお願いを片っ端から叶えていくのか?」
「……いいえ」
それはパリの店長にも言われたことだ。
「そもそも暗黒都市に“政治”なんてものはない。女王が創る永遠の夜があって、そこに有象無象の魔物が集っている、その状態が“暗黒都市”だ。階級も組織も悠久の暇潰しに過ぎねぇし、本来そんなものがなくたって女王は困らない。彼女はそこに在るだけで、在ることは絶対だからな」
とにかく時間が有り余ると閑なんだよなぁと大男があごを掻き、不思議の国の仕立て屋が後を継ぐ。
「お客様相談窓口なんてないし、運よく力のある魔物に助けを求める声が届いたって、助けてもらえるかはそいつの気まぐれによるからねぇ。現に今回はヴァルもユニヴェールも察知していたけどどちらも動かなかったわけだし」
「吸血鬼は気位が高くてワケの分からねェ滅びの美学を持ってて、関わり合いになると面倒くせぇからなぁ。醜態晒して助けてもらうくらいなら滅んだ方がマシだという輩ばっかりで、助けてやると逆に恨まれるしな。タチ悪ぃ」
過去に何かあったとしか思えないフェンリルの発言だが、その影でシャムシールとアスカロンがコソコソ交わしていた。
「矜持なんてない吸血鬼もいるけどね、ロートシルト卿とか」
「まぁな。あれは例外ってわけか」
「ロートシルト卿が特別ってなんかやだね」
「あぁ嫌だ」
だがそれっきり空気の振動は途絶えた。
星の瞬きも、水鳥のあくびも、フクロウの説教も、狸の足音も、城と湖を覆う深い霧が包み隠してしまったのだろう。
先の見えない蒼と灰色の霧が。
「分かりました。話を戻します──」
マルグリットは口元で両手をあわせて白い息を吐いた。
寒さを感じ始めたのは、気温が下っているからだろうか。
「貴方は、生贄として差し出された娘たちの血液が変質していたと見るのですね?」
「あぁ」
「ということは、娘たちが選ばれてからここに寄越されるまでの間に、ヴァチカンの介入があった可能性が高い?」
シャムシールへ目をやると、彼は大きく首を縦に振ってきた。
「それはつまり、ヴァチカンはこの町の人間が吸血鬼と契約して生贄を渡していることを知りながら、その契約を自分たちが開発した薬の実験として利用した──そういうことになりませんか?」
あえて、ヴェルトロには背を向ける。
「ヴァチカン単独で行ったのでしょうか。それとも領主や町の代表は、町の人々は、知っていたのでしょうか」
「もうひとつ教えてやろうか、お嬢ちゃん」
何が楽しいのか、酔っ払いの狼がさらに眠たげな目で手を叩いた。
ひとつひとつの動作がいちいち何かを壊しそうなほど荒い。
「俺がずっとここに居座っていたせいで、聖なる連中はこの城に近付けず、吸血鬼がどうなったのか確認できていない」
「マルグリット皇女がここに送られたのは遊びじゃない」
仕立て屋の美しい声は背後からした。おそらく、ヴェルトロの横。
「皇女も実験の一部、そしてフランスのためでもある」
「──それは違います!」
「へぇ〜」
思わず声を上げて否定してしまったのは、店長の誘導に引っかかったヴェルトロの過ち。
それ以前の部分を肯定することになってしまうのに。
「えっ、あぁ、いや、えーと」
「分かっています。私も実験の一部なら、ヴァチカンがフランスに加担して私を吸血鬼に食べさせようとするなら、ヴェルトロ・レンツィ、貴方が私の護衛を任じられるはずがありません。貴方はたぶん、そういう謀には向いていないもの」
彼の根底はきっと“良心”だ。
少なくとも、他人にそう感じさせる人間だ。
しかし、彼の良心とヴァチカンの使命と人々の罪とは別問題だ。
「シャムシール、アスカロン、頼まれてくださいますか?」
「いーよ」
マルグリットは遠くを見つめた。
未だ夜の眠りの中にある山岳の町が浮かび上がる。
昏い、昏い、昏い鐘の音が静かに染み渡る町。
「それと、フェンリルのおじさまも」
「…………」
藍色の目をした魔物が口端を上げた。
◆ ◇ ◆
「ユニヴェール卿は知ってたんだ?」
「さすがに詳細までは知らんだろうがな。教会は娘たちを生贄に出した、あいつはここの吸血鬼たちを生贄に出した。そういうことだ。どちらも、ファウスト二世の実験の成否を確かめるために」
城から一行が去り、狼と仕立て屋は城の上階で時を待っていた。
狼はバルコニーから森と湖を見下ろし、仕立て屋は部屋で椅子に腰かけている。同じく椅子に腰かけている吸血鬼の死骸の隣に。
「彼はどうしてアスカロンとシャムシールを寄越したのかねぇ? 自分で来れば早いのに」
「俺の立ち位置を確かめたんだよ。すぐ反逆するつもりなのか、大人しく暇潰しするつもりなのか。あいつ本人が出てきて、俺が反逆するつもりだったらどうする? 暗黒都市の番犬である以上、何かしないわけにはいかなくなるだろう」
「物事には楽しみ方ってものがあるからねぇ。つまらない時に闘っても、つまらない。あぁ、そういうわけ」
「それにアスカロンやシャムシールを寄越されたんじゃ、例え反逆するつもりだったとしても手も足も出ないだろ。おじさんは可愛い魔物には寛容だから」
「…………」
狼が身体を反転させると、吸血鬼の抜け殻の髪をくるくると弄る仕立て屋の細く細くなった双眸と目が合った。
「──その吸血鬼はお前にやるよ。そいつが城主だった男だ。最期の望みはヴァチカンへ渡らないこと」
「ありがと。じゃあ、入り口の吸血鬼がユニヴェール卿行きか」
ふっと肩で息を吐いて、男が立ち上がる。
「君が帰ってきてくれると、昔みたいに大きな仕事がしやすくなるから楽しみだよ」
「……何が欲しいんだ?」
「そうだねぇ。最終的には──」
バルコニーへ出てきたその男が、眼下の景色へ目を落とす。
両手から零れる豊かな水、果てなく続く両腕で抱えきれない木々の群れ。
「神に剣を突き立てたユニヴェール家と神の代理人であるヴェルトール家、その白鳥の歌を一対で紡げたら、素晴らしいと思わないかい? 絶対にとんでもない高値が付く」
夜明け前の底冷えにさらわれているオリエントの黒髪に笑い声が絡む。
「手伝いの代償はもちろん払うから」
連続するヨタカの声を聴いて、一拍。
「君の力を封印している女王の枷を、ひとつずつ解いてあげる」
「…………」
狼は背を反らして仕立て屋の顔を見た。
「解き方知ってんのか?」
「ううん、まだ知らない」
「…………」
蒼い森と湖と城、目覚めは近い。
◆ ◇ ◆
カプラの中心近くにあるその屋敷は、常緑の月桂樹に囲まれている。悲劇のダフネにして、アポローンの永遠の愛の証の木。
「こんな時間にお集まりいただきありがとうございます」
そしてこの夜はいくつもの馬車にも囲まれていた。
「領主様、遠くへご訪問になっていらしたのでは? ご無理を言って申し訳ありませんでした」
町の規模にしては大きな屋敷の、これまた大きな広間。
パリの貴族たちの屋敷のような華美を競う色はなく、ごく一般的な調度で整えられたその場に集められたのは、この地域の領主、町の代表者たち、囚われていた娘たちの両親、犠牲になった娘たちの両親。
「そんな、謝罪をいただくようなことでは」
「ご令嬢があの城の吸血鬼に誘拐されてしまっては、来ないわけには行かないですものね」
「え、えぇ……彼らは何故こんな無茶苦茶なことを……、ご説明いただけるんですよね?」
「はい、もちろんです」
恰幅が良すぎるその男は、さっきからひっきりなしに汗を拭いている。
「代表者の皆様も、それぞれご家族を誘拐されてしまってさぞかし落ち着かないことでしょう。こんな真夜中過ぎに召集させていただいて申し訳ありませんが、少しだけ辛抱してくださいね」
円卓にそろった大人たちを前に、少女がいたわりの笑みを見せる。
ここに集められた偉い大人たちは皆、今夜急に家族が誘拐されてしまったのだ。あの城の吸血鬼に。
まぁ、そうでもなければこんなに素直に集まらないだろうが。
「それでは、始めます」
少女が厳かに宣言し、しかし彼女が次に放った言葉はいきなり辛辣だった。
「まず、今夜、皆様の大切な方々がいきなり誘拐されてしまった件について、私マルグリット・ドートリッシュやヴェルトロ・レンツィの交渉が失敗したからではないことを断っておきます」
神聖ローマ帝国の皇女に猜疑の眼差しを送る強者はいない。皆、視線を伏せている。
「吸血鬼たちは大変立腹しておりましたよ。こちらは契約を守り町を襲わず魔物まで排除していたのに、お前たちは女たちに薬を飲ませ、彼らを滅ぼそうと謀ったと。重大な契約違反だと」
『!?』
『…………』
円卓の一部が意味が分からないという顔を見せ、一部が無意識に息を呑む。
「……では貴女は、我々に永遠に吸血鬼の下僕でいろと言うのですか」
息を呑んだ領主は、即座に開き直ることを決めたらしかった。この恵まれない地理を体現する卑屈な目が、マルグリットを上目に見る。
「ずっと、私たちも、子どもたちも、奴らの家畜でいろと」
「吸血鬼を滅ぼす方法はヴァチカンから打診されたのですね?」
重ねられた問いによって、その場の全員が薄々気付き始める。
これはゆるやかな尋問だ。
質問権はこの小さな娘にあって、彼女は決してそれを譲らない。
「……はい。素晴らしい薬が出来たから、と」
情に訴えることを諦め、領主が折れた。
彼の言葉に、円卓の上のいくつもの目が少女の後ろに控えるクルースニクをちらちらと見る。だが、透明な碧眼を遠くの一点に据えたまま、聖なる狩人が言葉を発することはない。
そこへ、
「それは……どういうことですか……?」
継ぎの多い上着を着た男が不安そうに口を挟んできた。
「我々が裏切ったって」
生贄となった娘の親だろう。
「ご両親でさえ知らされていなかったのですね」
マルグリットの言葉はヴェルトロへ。彼は無言を肯定として返してくる。
ヴァチカンの意思を知っていたのは、領主と、円卓の一部である町の代表者たち。
彼女は円卓の上で手を組んだ。
一度レースの袖口に目を落とし、ゆっくりと顔を上げる。
「ヴァチカンは薬を開発しました。その薬を人間が飲むと血液が変質し、その変質した血液を飲んだ吸血鬼は、人間の血液そのものを受け付けない身体になってしまうのです。その結果どうなるか、そうです、血液を摂取できない吸血鬼には滅びあるのみ。それを実証するため、ヴァチカンはこの町に協力を要請していました。生贄となる娘たちに薬を与え、その血液を吸血鬼が摂取することにより、本当に滅びるかどうかを試してみようということです」
聖なる狩人は、ひとりの生贄のためではなく、迷える万民のために存在する。
「誰かが犠牲になればこの町は吸血鬼から解放されるかもしれない。しかし同時に重大な欠陥です。解放されるためには誰かが犠牲にならなければいけない」
「……仕方のないことなんですよ……。今までと何が違うでしょう。我々が生きるために犠牲になった娘たちと、契約を終わらせるために犠牲になった娘たちと、何が違いますか?」
領主が肩を震わせた。
「ヴァチカンの実験に利用されたという点が違います」
「例え利用されたのだとしても、それでこの町の悲惨な歴史に終止符が打てるのです。意義のある犠牲ですよ。……決して無駄死にではない」
「契約のことは町の人々誰もが知っています。ですが、実験のことはほとんどが知らなかった」
「知っていたとして、何かが変わったでしょうか」
「ご両親はそれで納得されるのですか?」
マルグリットの声に咎めの色はない。抑揚はあるが激情はない。
夜の真ん中に漣立つその部屋は、さながら修道女に懺悔している聖室のようだった。
「……はい。町の人たちが救われるためです、仕方ありません」
さきほどの男とは別の、やつれた男が首を垂れた。
「そうですか。他のみなさんも同じですか?」
娘たちの親は、苛酷で質素な暮らしが滲む身なりで分かる。
それらがばらばらとうなずいた。
どこまでが美徳に強制されたうなずきで、どこまでが本心なのかは汲むことができない。表情に乏しい人々の反応はあまりにも力なかった。
静かに静かに、波紋さえ浮かばない水の下で自分たちの命が天秤にかけられていてもなお、仕方のないことだと涙を飲む姿は称えるべき山羊なのか、ただの屍なのか。
「では、質問を変えます。ボージェさん、調べたところ、貴方のお嬢様はすでに嫁がれていてこの町にはいらっしゃいませんね? このお屋敷にいらっしゃる娘さんは貴方と血縁のない方です。しかもごく最近お屋敷に招き入れられた。それでは私は、一体どなたの身代わりになったのでしょう」
「……それは……」
屋敷の主が円卓に手をかけ腰を浮かせ、しかし言葉は勢いをなくしてとうとう喉の奥から現れることはなかった。
「大丈夫です、おかけなさい」
少女はゆるやかに手で指し示した。
そしてその手を領主の方へ返す。
「領主様、貴方の家令はとても優秀ですね。とても細かく帳簿をつけていらっしゃるようです」
彼女は控えていた少年から紙束を受け取り、
「──この大金の受け取りは何がありましたか? 私が記憶する限り、相手の方はフランス王国でそれなりに地位を築いていらっしゃる方ですよ」
再び彼へ戻す。少年は紙束を領主の席へ運び、わざわざその項を指で示す。
「…………」
「この町は特段の産業もなく、山深過ぎて農地も充分確保できない。巡礼路からも外れていて旅する巡礼者たちで潤うこともない。少しでも町の財政を豊かにしたいというお気持ちは分かります」
「仕方なかったのです。この辺り一帯、もうどうにも納めるべき金が不足していて……」
「私を吸血鬼のエサにする代わりにフランスから受け取ったお金は、すべてこの町のために使う予定でしたか?」
「……え、えぇ! それはもちろん!」
「!」
領主の裏返った叫びを聞くや目を吊り上げた少年を、マルグリットは手で制する。
「そのおつもりならば、良いのです」
告げながら、彼女は窓の外を見ていた。
夜が白み、さらに冷えてきた。
空気が研ぎ澄まされ、夜と朝の深奥へ向かって急激に澄んでいく。
世界が、女王の手から離れようとしている。
「ごめんなさい、私は始めに嘘を付きました。もうあの城には吸血鬼はおりません。優しいお嬢様たちの犠牲が実を結んだのです」
疲弊は、歓声すら生まなかった。
ただ、いくつかの湿った息が漏れただけ。
慟哭も嗚咽もない。
世界の踏み台になった町は、静かにその役目を終える。
しかし、終わっても、町が背負っていた十字架とこれから背負うのだろう十字架の重さは何も変わらない。
「誘拐された方々は皆無事であの城におります。怖がらず迎えに行って差し上げなさい。番人にマルグリットからの遣いだと言えばすぐに渡してくれるでしょう」
狼は退屈な役を軽く引き受けてくれた。
人々が素直にすべてを認めたら人質を返してもらいに行くから、それまでアスカロンがさらってきた人と地下牢の娘さんたちを預かっておいてほしい──。
「本当ですか!? ならばすぐに!!」
誰も彼女の狂言を非難することはできない。
慌てふためきながら立ち上がろうとする偉い大人たちを前に、彼女は言葉を続けた。
「“仕方がない”」
明瞭に発音されたそれは、凛と突き刺さる。
「これは人を殺めることができる言葉です。罪を罪でないかのように覆ってしまえる言葉です。まるで、あの城を霧が隠してしまうように」
憐憫と慈愛と欺瞞と諦観に満ちた霧。
どこにでもある、人の世に薄く広く漂う霧。
「けれどそこに城は存在しています。罪も存在しています」
未来の薔薇園へと続く道を覆う霧の下には、累々たる山羊の屍。
物言わぬ十字架の骸。
「それを、お忘れなきよう」
◆ ◇ ◆
「吸血鬼の死骸があったことを確認できただけでも良しとするか」
「えぇ、そうですね」
粗末な宿屋の二階に朝陽が差し込む。
「すみません、さすがにあの城に居座っている化け物の正体が北欧の狼ではそれ以上踏み込むわけにも行かず、回収は無理でした」
徹夜になった目をこすりながらヴェルトロが謝罪すると、寝台に身を投げ出していた一人が破顔する。
「ヨハンは解剖したかったかもしれんが、危険を冒すほどのことじゃないさ。俺が行ってもコイツが行っても結果は同じだった」
コイツ──男がアゴで窓際に立っているもうひとりを指す。
物騒な会話ではあるが、この宿には他に客はいないから聞かれる心配はない。……そもそもカプラに旅人などほとんど来ないのだ。冬という時期の悪さも相まって、彼がマルセイユから異動して以来、ほとんど。
「フランスが半ば本気で皇女を吸血鬼に喰わそうとしていたのは誤算だったが、そのおかげで城の中を見に行く口実ができたとも言えるし、吸血鬼が全滅していることも確定したし、北欧の狼が起こされていることも分かったし、本当に人生は何がどう転じるか分からんもんだなぁ」
「マルグリット皇女は、ややこしくなるから今回のことは公にするおつもりはないそうです」
「お嬢ちゃんの賢明な判断だ。このことはいつかハプスブルクにとって有利な条件になる」
眼識ある男が寝転んだまま含んだ声音で言い、そしてわずかに調子を変える。
「それよりも、ここでの仕事はこれで終わりだ。君が真面目に契約の履行を監視してくれたおかげで、良い結果が得られた」
「我々が最終確認に訪れる必要もありませんでしたね」
「そういうわけにはいかんだろう、仮にもこの計画の責任者と副責任者なら」
「いえ、私は特にこれといったことはやっていないので……」
ふたりの上司に褒められるとむずがゆい。
「慌ただしくてすまないが、もうここに用はない。君の次の勤務地はヴァチカンだ」
「身に余る光栄です」
ヴァルトロが恭しく胸に手を当てると、見計らったかのようにコツコツと扉を叩く音がした。
振り返れば、音の主はすでに扉の内側にいた。
開けて入ってきたのではない。そこに現れたのだ。
「……アスカロン」
主に土産でも持って帰るのか、片手に大きな包みを下げたその男は、名を呼んだヴェルトロの方には目もくれず、未だ寝台に転がっている男を見据えている。
「アンタがお出ましとはね、クロージャー・ミルトス。ソテールが隊長をクビになったのを機に、ヴェルトールの称号を奪うつもりか?」
ユニヴェールの三使徒、季節に逆行して枯葉色の外套をまとう彼は、粗末な寝台で足を組んでいる男をじっと映している。あの城で寸劇をしながらフェンリルやシャムシールに対していた時とは全く違う、風も凍る水面の静止。誰も息さえしてはならぬ──。
「まさか」
指名を受けたクロージャーが黒髪をかきあげ、鼻先で笑う。
「甥っ子から看板を取り上げるつもりはないね。あの看板は重すぎて本物しか背負えない。こっちから願い下げさ」
「しかもカリス付きとは」
おまけのように言われて、窓辺の始末人が一度目を伏せゆっくりと視線を彼にやる。
「こんな辺境の町のくせにデュランダルが二人もそろって──」
台詞を区切り、そこでようやく彼はヴェルトロを上から下まで眺めてきた。
「アンタもデュランダルか」
「えぇ」
大して驚いた様子はなかった。
「三人もそろって、随分大事な実験だったと見えるな?」
「まぁ、まだ欠陥はあるが。吸血鬼一匹殺すのに、人間一人の犠牲が必要になるのはなぁ」
「ヴァチカンは赦すのか?」
「未来の犠牲者を救うため──大義名分はあるから、赦すかもしれんね。それは我々の預かり知らぬところの話だよ」
「アンタたちが狩った方が効率がいいんじゃねぇの」
「そうでもない」
ようやく男が寝台から身を起こす。
「この話はそう時間がかからずに魔物どもの間に広まるだろう。だが吸血鬼には薬を飲んだ人間が誰かは分からない。恐ろしいと思わないか? 飯を喰うのに毎回命を懸けて賭けをしなきゃならないんだぞ。もし外れだったら、餓死することになる」
「一匹あたりの食事の回数を抑える効果はあると思いませんか」
「殺すことだけが好きな奴もいるけどな」
「ヨハンも我々もバカじゃない。破れた網で魚を獲る趣味はないね」
ヨハン・ファウストの薬によって吸血鬼が本当に餓死するのかという実験であって、これで吸血鬼を絶滅させられるかの実験ではないのだ。
一匹滅ぼすのに人間一人の犠牲は確かに大きすぎるし、暗黒都市にだって医者はいるだろうから、経口がダメなら輸血という手段に出るかもしれない。もしかしたらそれは餓死回避に有効かもしれない。
──ヴァチカンが許容する手段で吸血鬼のすべての退路を断つには、まだ、もう少しだけ時間が必要なのだ。
「しかしお前もデュランダルが三人もいてよくこの部屋に入ってきたな」
「シャムシールはお使いに来たが、俺はお使いに来たわけじゃねぇからな。それにアンタたちは今俺を滅ぼしてユニヴェールと事を構えるほど考えなしとは思えない」
そこで言葉を切って、彼は八重歯を見せる。
「何だったら三人まとめて相手してやっても俺は困らないけどな」
そして部屋を見回し、眉根を寄せた。
「カリスがいてミトラがいねぇってことは、他の地域でも同じような実験をやってんだろ。えげつねぇー」
「ファウスト二世のご意向さ。それにごく自然な形で魔物たちに広報する必要があるからな。研究室の中でやってたんじゃ意味がない」
クロージャーが当然だと肩をすくめ、
「同朋の死を観察する貴方たちと、お互い様でしょう」
カリスが自虐ともとれる冷水を浴びせる。
だがまるで効いていないアスカロンはニヤついたまま聖印を切ってきた。
「まぁせいぜい頑張れや。神と人間のために。──主の国は終わることなしってな 。Amen.」
パーテルの魔物は、今度は律儀に扉開けて出て行った。
「アスカロン!」
軽く無視したのを怒ったのか、何故か追いかけてくるヴェルトロに対し、アスカロンは意地悪く急に歩みを止めた。
「あぁそうだ。シャムシールがアンタに謝っといてくれって」
「謝る?」
ぶつかりそうになって壁に手を付いたクルースニクが、その頭の上に疑問符を浮かべる。
「フランスの手先だって疑ってごめんね〜♪ だとさ。まぁそもそも教皇の反勢力を匿ってるフランスにヴァチカンが手を貸すわけがねぇんだよな」
「いや、それは……あ、でも彼はどこに?」
「あぁ、フェンリルが早速手配してくれた菓子の山を馬車に押し込んで、マルグリットと一緒にフランドルへ発ったぜ」
「えええー!」
クルースニクに多い前のめりの叫びではなく、後ろに引いた情けない叫び。
「私、皇女のお供を仰せつかっているんですけど! フランスが何をしてくるか分からないから!」
「そりゃあ……早く追いかけた方がいいんじゃねぇの?」
「皇女にはお伝えしてあったのに、何も置いてきぼりにしなくても……」
蚊の鳴き声は聞いたことがないが、たぶんこんなかんじ。
「……送ってやろうか。向こうは普通の馬で行ったから、暗黒都市の馬なら追いつくと思うが……」
思わず同情して言ってから気が付く。
これは今までのデュランダルにはなかった特技だ。
「いいえ、大丈夫です。追いかけます!」
弱気ではあるが、立ち直りも早いらしい。
「あぁそうだ、ひとつお聞きしたかったんですけど」
宝石のような碧眼は、それゆえに光を反射して意図が読めない。
「貴方たちがユニヴェール卿に忠誠を誓うのは何故です? クルースニクを止めて、死んでまで」
きっとカリスあたりから昔話を聞かされているのだろう。
未だに彼らが閉じることのできない褪せた日記の一部分。
「アンタたちが神に忠誠を誓うのは何故だ? 善良な人間を止めて、あらゆる罪を負うデュランダルになってまで」
「では貴方は、ユニヴェール卿に命じられれば滅ぶことも厭わない?」
「そりゃ滅ぶくらい構わねぇが、そもそもそんな事態は起きねぇよ」
「?」
アスカロンはクルースニクに背を向けた。
手を振りながら階段を降りる。
「俺が滅ぼされるくらいの相手だったら、奴は自分で乗り込むからな」
「……なるほど」
階上でつぶやかれる、清々しいほど裏の気配のない得心の声。
あの悪魔の巣窟で生きていかれるか若干心配ではある。
その頃、旅人を轢きそうな勢いで馬車は山を下っていた。昨日まで憂愁を帯びていたフランドルへ向かって。
車輪が道のくぼみを走ってひと跳ねするごとに、窓から焼き菓子やらタルトの破片やらゴーフルやらが転がり落ち、子どもたちの盛大な笑い声が零れる。
木々の間に逃れた旅人はしばらく馬車を見送り、そして再び山道を登り始めた。
目深に被ったつば広の帽子の下には虚ろな仮面。
揺らめく防寒外套は黒。風にちらりと翻る中には刑場の緋色。
◆ ◇ ◆
春雨に煙るパーテルの町は、昼間だというのに暗い。
「もしヨハンが吸血鬼に対する画期的な薬を開発したら、パーテルの民も、パリの民も、カプラの犠牲のことは知らぬまま喝采を送るだろう」
ガウンを羽織った吸血鬼は、屋根や舗石を叩く雨粒を見下ろす。
「生贄を差し出していた当人たちでさえ、生贄本人でさえ、それが世界のための磔刑だとは知らなかった。マルグリットが関わらなければ」
食堂のテーブルでは、メイドが葡萄酒の瓶に髑髏マークを描いた紙を貼っている。
アスカロンがあの町から持ち帰ったもので、生贄となった娘たちが必ず飲まされていたもの──対吸血鬼用の薬かも──だそうだ。
「山羊の存在すら知らず、誰のための、何のための山羊かも知らず」
温かい水の流れが窓のガラスを伝い、吸血鬼の白い指がそれをなぞる。
「ゆえに世は、本日も晴天なり」
すると、彼の背後からメイドがぼそっとつぶやいてきた。
「今日は雨ですよ」
THE END
Back Menu
Home
メム店長初出 100のお題−015.主従より「聖」
BGM by Thomas Adam Habuda [Floating Skulls, Rising Souls] Fringe Elements Trailer Series [Dominion]
Cavendish Music [Search for Justice] Within Temptation [Forsaken]
Copyright(C)2012
Fuji-Kaori all rights reserved.
|